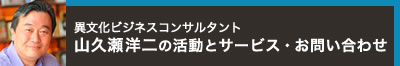1946年の晩秋、一人の男がハバナの港に降り立った。男の名前はラッキー・ルチアーノ、一時はニューヨークを拠点に全米を牛耳っていたマフィアの大物。出身はイタリアのシシリーである。彼は、8ヶ月前にアメリカからイタリアへ強制送還されたばかりだった。
迎えにきたのはルチアーノの片腕で、ニューヨークのシマをとりしきるマイヤー・ランスキー。「トムが大統領候補だって。なんとかならないのかい」ルチアーノはランスキーと抱き合ったあと、そうつぶやいた。トムとは、当時のニューヨーク州知事トーマス・デューイのこと。彼が検事だったころ、ラッキー・ルチアーノは訴追され服役させられた。
刑務所に送り込まれたルチアーノを救ったのは、第二次世界大戦だった。ドイツのスパイが港湾労働者にまぎれてアメリカに潜伏しているという情報を得たアメリカ海軍が、東海岸の港を実質的に管理していたマフィアに、スパイ摘発への協力を要請したことがその発端だった。しかも、海軍はヨーロッパでの反撃のため、シシリーへの上陸を計画しており、そのためにもマフィアからの情報提供を必要としていた。ラッキー・ルチアーノは獄中からランスキーを使ってマフィアを操っていた。海軍の情報将校から依頼を受けると、ルチアーノは仲間を通じて、シシリーのマフィアの大物幹部のアメリカ海軍への協力を取り付けたのである。この功績で、彼には恩赦が与えられる。
キャデラックの後部座席に深々と腰掛けてラッキー・ルチアーノは続ける。「トムは、俺の恩赦をしぶしぶ認めやがった。でも、アメリカから出て行くことを条件にな。あいつがいる限り、俺はニューヨークには戻れない」トーマス・デューイは、48年の大統領選挙の共和党の有力候補と目されていた。結果はトルーマンに破れてしまうが。
ところで、ルチアーノがハバナにやってきた理由は、マフィアの幹部との会合に出席するため。彼はその会合で、ランスキーの親友、ベンジャミン・シーゲルの粛清を考えていた。シーゲルはその昔、ルチアーノの組織のヒットマンとして頭角をあらわした。しかし、彼はラスベガスのフラミンゴホテルに過剰に投資して損失を膨らませ、マフィアの中での信用を失っていたのである。ルチアーノは、このハバナ会議でなんとか盟友ランスキーを説得し、シーゲルの粛清を認めさせる。このあたりのいきさつはゴッドファーザーⅡのモデルにもなったことでもよく知られている。1947年6月、シーゲルはビバリーヒルズの自宅で何者かに射殺された。ラッキー・ルチアーノはその後もアメリカに近いハバナに居住したがっていた。しかし、アメリカ政府はそんな彼の動きを察知し、キューバ政府に圧力をかけ、彼をイタリアに送り返す。その後ルチアーノはナポリで生涯を終える。
あのハバナ会議から64年。私は、2年前の夏にハバナにいた。今、ハバナには、そんな強者 (つわもの) の陰はない。1959年にフィデル・カストロがキューバを共産化したとき、キューバとアメリカとの蜜月は終わり、以後アメリカとは断交に近い状態が続いている。
ハバナに到着した翌日の午後、街を散歩していたとき、だんだんと陽が陰ってきた。公園の街路樹がざわつき、生暖かい風が頬をなめる。スコールの予兆だった。急いでホテルに戻ろうと、目抜き通りのオビスポ街を目指して歩きだす。
「おい、チャイナタウンなら向こうだよ」
ハバナの男たちは、アジア系の顔をみると、こう言って声をかける。人懐っこいのはいいが、これにはちょっと閉口する。アジアの人が一人で歩いていれば、それだけで人々の好奇心をそそってしまうのだろう。
私は、マフィアの暗躍していた頃のハバナの面影を求めて街を歩いていた。しかし、それは探すまでもなかった。ヘミングウェイも愛したというラムをベースにしたダイキリ、そしてルチアーノやランスキーも楽しんだはずの葉巻の味は、今も変わっていない。街には、アメリカが経済封鎖をする前の50年代のキャデラックやオールズモビルが今なお走っている。どれも、ポンコツだが、そのちょっと錆び付いたような原色のカラーが、不思議と街に合っている。
やはりスコールがやってきた。雨は風を止め、海岸に打ち寄せる泡立った波の香りをかき消した。オビスポ街に間に合わず、近くの野菜市場に駆け込むと、野菜売が側におくラジオカセットから、ブエナビスタ・ソーシャル・クラブを思い出させるラテン音楽が流れてくる。
ハバナから強者は去っても、アメリカの50年代の残滓は今も街に息づいている。その面影が、古き良き時代の風景のままに、時間が止まったように街は凍結されていた。却って、カストロの後、キューバがグローバル経済の洗礼を受けてしまえば、こうした風景は激変するはずだ。古いキャデラックも今のGMの新車に変わってしまう。
皮肉なものだ。数年後、今のマフィアがコンピュータを持ってエコカーに乗ってハバナにやってくるかもしれない。