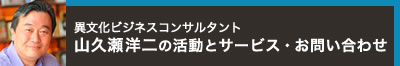サンクトペテルブルクにあるドストエフスキーが住んでいたアパートのすぐそばに、食品市場がある。
ドストエフスキーもそこに立ち寄って黒パンに紅茶を買っていたかもしれないなどと思いながら、売り場を巡った。
白衣に白いスカーフをかぶったおばさんが並んでいるところでは、にしんの薫製やイクラなどを売っている。
イクラはロシア語でもイクラ。
そんなことを覚えたのは、ニューヨークはブルックリンにあるリトルオデッサでのことだった。
リトルオデッサとは、ニューヨークのブライトンビーチにあってウクライナやロシアからの移民が集まり住む地域のこと。そこにも、サンクトペテルブルクにあるものと同じような食料品店があって、お目当てのイクラも売っている。
90年代、リトルオデッサで買うイクラは極めて安かった。
確か、タッパーにぎゅうぎゅうに詰めてもらっても、20ドルもしなかったはずだ。だから、不謹慎な話だが、余ったイクラはニューヨークのアパートにいた愛猫の垂涎の的となった。
ブライトンビーチはブルックリンの突端にあって、大西洋に面している。
それは丁度浅草の花屋敷を大きくしたようなレトロな遊園地、コニーアイランドの隣に位置している。
コニーアイランドでの食といえば、ポーランドからの移民が19世紀の終わりにソーセージをパンにはさんでそこで売り出したところ人気を博し、瞬く間にアメリカ中に広がった食べ物がある。ホットドッグのおこりである。
サンクトペテルブルクは10月でもともすればとても冷え込む。
ドストエフスキーのアパートの中を歩くとき、なぜかアパートの玄関で雪にぬかるんだ靴の汚れを落とす文豪の姿が瞼に浮かぶ。そして、作家は台所にあるサモワールで湧かしたお湯でお茶を飲む。
おっと、そういえばニューヨークのグリニッジ・ヴィレッジにあるカフェレジオというイタリア系のカフェの奥には、なぜか大きなサモワールがあった。あのカフェでエスプレッソを飲みながらよく知人と話をしたものだ。
そのカフェからほんの2分も歩けばワシントンスクエアに至る。
スクエアではストリートパフォーマンスの前に人だかりができ、木陰ではチェスに興じる男達が。
そんな広場の角にはとても枝振りのいい楡の木が。その木のニックネームはハンギングエルム。19世紀にそこで公開の絞首刑が行われていたことからその名がついたが、今ではその事実を知る人は少ない。
今、東京に住んで、サンクトペテルブルクとニューヨークという、一見何の関連もないこの二つの街でのことを思い出し、心の中の透明な線で繋いでみる。
ニューヨークに住んでいた頃の友人と久しぶりに連絡がとれ、先週東京で再会したことが、私を刺激したのかもしれない。
その男は、サクソフォーンプレイヤーになろうとニューヨークに渡り、夢半ばでふと手にしたカメラに惹かれ、街の写真をとるも、それもまた生活の糧を稼ぐまでにはいたらず、そのままハワイに渡った。
しかし、今では日本からハワイを訪れる新郎新婦の記念写真をとって見事に生活をしている。
そんな彼と「ニューヨーク歴史物語」という一冊の本を造ったことがあった。
本の中ではニューヨークの歴史上の蘊蓄を語り、彼の写真とありし日のニューヨークを映した古写真を沢山ちりばめた。
ロシアや東欧から流れてきたユダヤ系移民の貧しくも逞しく生きる姿を捉えたジェイコブ・リッツの写真は特に印象的だ。彼こそは、フォトジャーナリズムの先駆けといってもいい。
あの企画の取材のため、友人の撮影に同行し、彼のお気に入りのホットドッグ屋で遅いランチをとったことがあった。そのあと、ブルックリンに足を伸ばし、コニーアイランドの錆び付いた遊園地を撮影した。
帰りに寄ったブライトンビーチ。曇天のなか街は重く錆び付いていた。ああ、グリニッジ・ヴィレッジに戻り、カフェレジオで暖かいカプチーノを飲みたいと思ったことを今でも覚えている。
あれから15年の歳月が流れてしまった。
再びサンクトペテルブルク。
あの日、ドストエフスキーの家を後に、ネフスキー通りをネヴァ川に向かって歩いた。大通りの右手にあるプーシキンがよく通ったというカフェに立寄る。
街はあのブライトンビーチのときと同じく薄暗くそして寒かった。
あれもすでに7年前のこと。
今年の秋、私は再び仕事でロシアを旅する予定だ。そして、あのときと同じように、ロシアからフランクフルトを経由してニューヨークに渡る。
そうだ、フランクフルトの空港では乗り継ぎで遅れそうになり、走ってゲートに行くと、「サンクトペテルブルクからの乗り継ぎでしたね」といって地上係員が私の名前を呼んだ。
ロシアからニューヨーク行に乗り換えたのは私一人だったのだろう。慌てるまでもなく、係員は私がゲートに急いでいることを知っていたようだ。
移民を産み出した国。そして移民が流れ込んだ国。この二つの国を代表する二つの都市、サンクトペテルブルグとニューヨーク、19世紀に逞しく生き抜いた人々の亡霊の透明の糸によって、やはり結ばれていたことを、飛行機の窓の下の雲を眺めながら今年確認するのも楽しみの一つである。