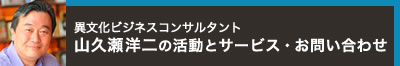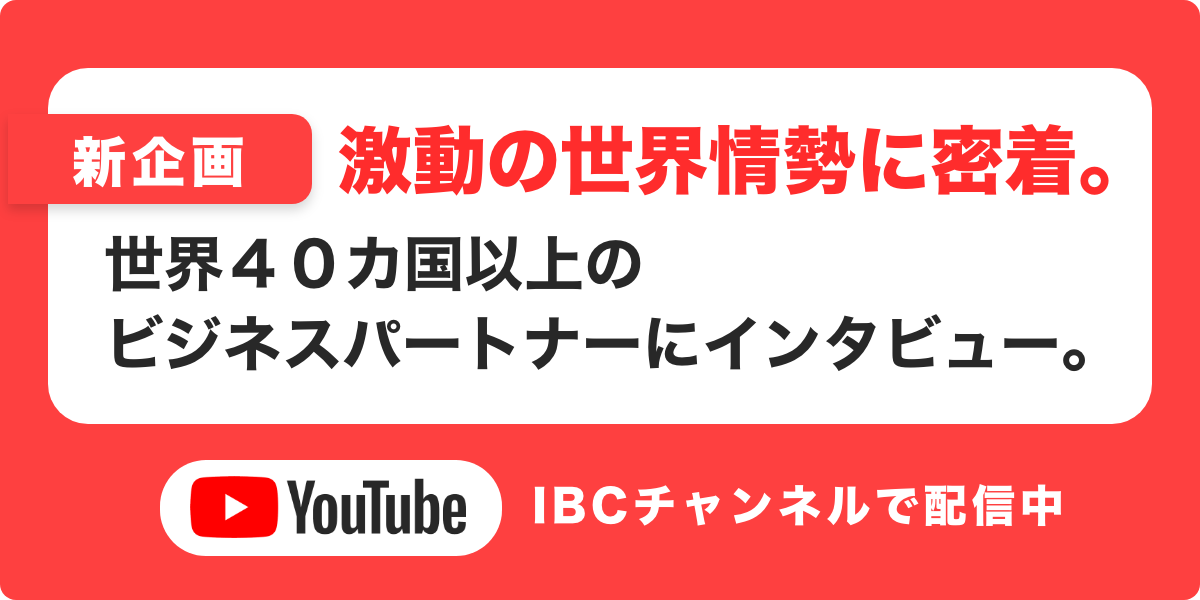Teams across Google are working on ways to unlock AI’s benefits in fields as wide-ranging as healthcare, crisis response and education.
(グーグルは、全社においてヘルスケア、危機管理、教育などの幅広い分野でAIの利点を引き出そうと取り組んでいる)
― Googleのプレスリリース より
とある教育ビジネス関係者によるAIツールへの指摘
一つの製品が開発されるとき、常に気をつけなければならないのは、その製品の汎用性や利便性は、その製品が作られた国や地域の文化の影響を強く受けているという事実です。
実にわかりきった指摘のように思えますが、現在でも我々はこのポイントを見落としがちなのです。しかも、自らが開発した製品が、そのまま海外にも通用すると思い込みがちなのです。我々の製品はこれだけ素晴らしいのだからユニバーサルな価値があると誤解するのです。
実は、この誤解が最も頻繁におきているのがAIの世界なのです。例えば、Googleのような世界企業がAIを駆使した教育ツールを開発・発売するとき、その発想の根本にはアメリカの教育文化やコミュニケーション文化がこびりついていることに気づく人は意外と少ないのです。
もし、あなたが天文学に興味があったとします。しかし、あなたの興味は天体を観測することで、天文物理学のカテゴリーではなかったとします。
今、生成AIでこうした個別のニーズに合わせて教育を受けようとしても、まずAI側では、あなたを理科系の人間だと評価して、いきなり高等数学や理論物理に関する課題を提供してくるケースが多くあります。
福岡県のとある地方都市で新たな教育ビジネスに取り組んでいる人が、最近このようにこぼしたことがありました。
実は、彼はGoogle本社が主催する
イノベータープログラムで、夏にプレゼンテーションをしなければならないのです。イノベータープログラムの中で、Googleが売り出しているAIツールの課題を指摘し、さらに有益な製品を生み出すためのアイディアをプレゼンしなければなりません。
彼のアイディアは、天体観測に興味がある子が失望しないような、個々のニーズに見合った、最適化した教育ツールの開発が必要だということを関係者に訴えることだったのです。

教育ツールにおける「ローカライゼーション」の課題
そのときに、彼の意見を聞いていたアメリカ人が、「そもそもそれは日本の環境にはマッチしないのでは」と指摘します。つまり、日本の社会はもともと集団で動くため、個々のニーズに最適化したツールを使用するには不向きな国なのでは、というのがそのアメリカ人の指摘でした。
確かに、日本には個人が何かにチャレンジすることを阻害するような環境がないわけではありません。例えば、一つのことに興味を抱いて集中する子どもがいれば、そのことで、他の教科の学習が疎かにならないかと教師や親は心配しがちです。その子の興味と個性にマッチしたソリューションを提供することを、結果的に怠ってしまう傾向がないとはいえないのです。
しかし、極めてドライに考えれば、そうした環境のある日本からの指摘があるからこそ、Googleでは自らの製品のイノベーションができ、より広範で多様な市場に拡販できるように工夫できるのでは、と私は反論したのです。であればこそ、この福岡県の小さな地方都市に住む人の指摘が注目されているのではないかと思ったからです。
このプロセスは、いわゆるローカライズ、つまりそれぞれの地域のニーズに合わせて商品を再点検し、調整することを意味します。AIの場合は、既存の商品に比べてより人間の言葉や思考に焦点を当てて開発するからこそ、このローカライズのプロセスを怠りがちになるのです。というのも、人間は一般的に、自らの育った文化の中で、それぞれが文化の洗脳を受けていることに対して鈍感だからです。
教育ツールを作成するときには、どのように先生が子どもを把握し、逆に子どもが先生とつき合ってゆくかという双方向からの分析が必要です。しかし、もともと多様な移民によって構成されているアメリカ社会では、個人の自己主張が日本とは比較にならないほど尊重されます。それは教師も生徒も、まさに同等に持っている権利ともいえるほどです。しかし、その方程式をいきなり日本の教育現場に持ち込めば、そこに思わぬ混乱がおきてしまうわけです。
言い換えれば、アメリカ人はアメリカの文化に、そして日本人は日本の文化から洗脳を受けているのです。その洗脳を、我々は「常識」とか「価値観」というふうに表現しがちなのです。
であれば、Googleが主催するイノベータープログラムで、日本の典型的な地方都市で教育事業に取り組んでいる人物の意見がいかに貴重であるか、容易に理解できます。
「これからは、先生が生徒を教育するというよりは、先生はコーチであり、コーディネーター、さらにはファシリテーターとなるはずです」
これは、Googleクラスルームの開発をよく知るアメリカ人のコメントです。
「個性に見合った最適化をするということは、ただその子の興味のある分野を伸ばすために照準を合わせる作業ではないのです。その子がどうして特定のことに興味を持っているかということを理解した上で、その子の人格形成全般により効果的に貢献できるようなツールが、これからは求められるのです」
アメリカ人の専門家はこう指摘します。

文化の独自性を新規開発のビジネスチャンスに
一方で、日本の教育現場ではAIという概念自体への誤解も多いようです。例えば、AIを導入することで、多くの教師は自らの仕事が増えるのではないかと警戒します。本来は仕事を合理化するためにあるAIツールをどのように使いこなしてゆくかというテーマについて、教師を教育するシステムが整っていないからです。
しかし、これも日本の一つの文化であるとすれば、日本人がより抵抗なく取り組める教師への支援補助ツールの開発も、イノベータープログラムでプレゼンできるテーマなのではと指摘できるはずです。
特定の文化を批判したり評論したりする前に、それを逆手にとってビジネスチャンスにする方が、より大きい利益を生むことにつながるように思えます。
そうした意味では、日本人がグローバルなビジネス環境で果たせる役割も見えてきます。
つまり、日本はただ日本として孤立しているのではなく、必ず日本と似たコミュニケーション文化を持った国があるはずだからです。そうであれば、日本の事例を正しく伝えてゆき、日本の課題を解決すれば、その経験は他の多くの国での市場開発にも応用できるかもしれないのです。
福岡の教育事業者によるイノベータープログラムでのプレゼンに、期待するところは大きいかもしれません。
* * *
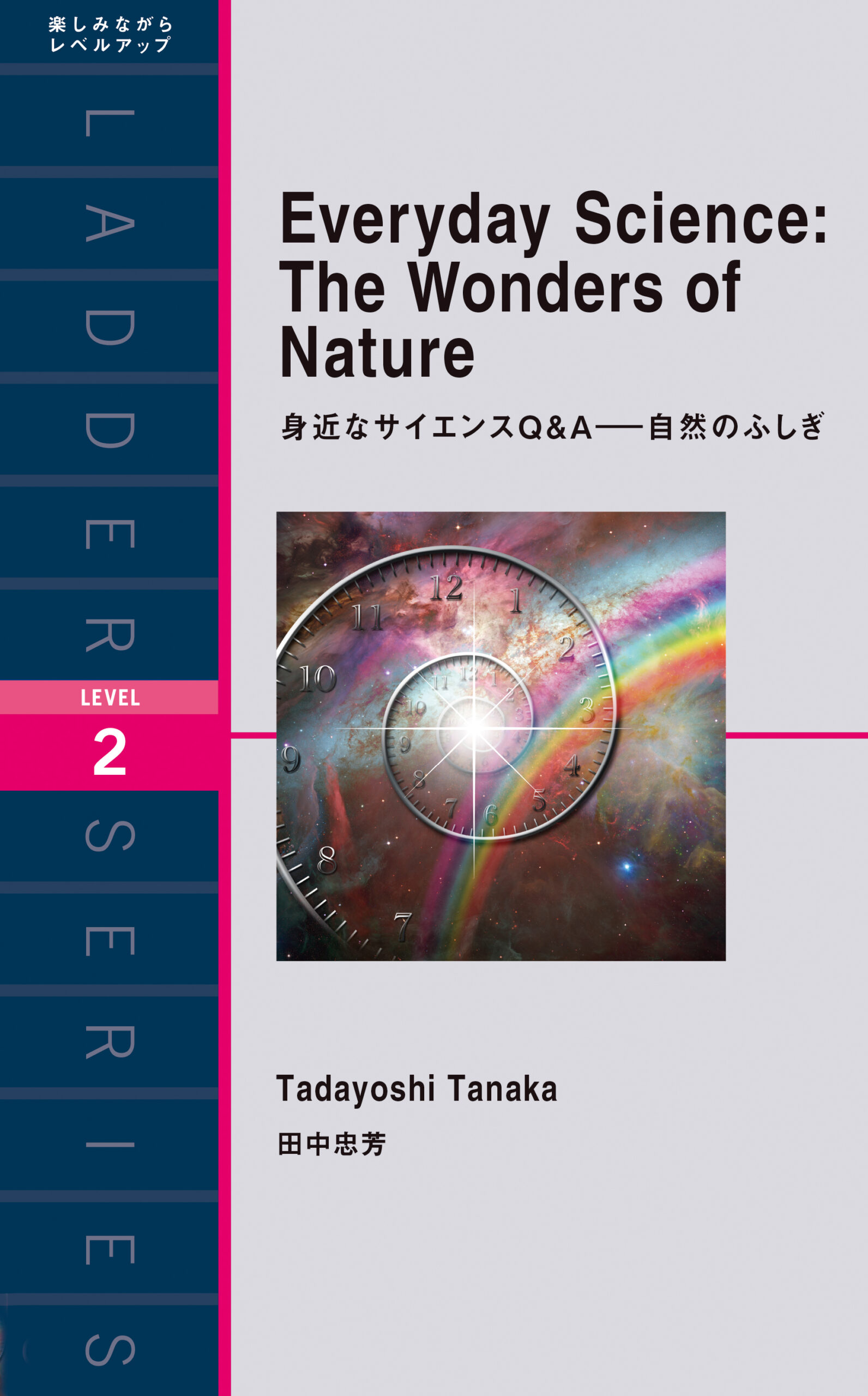 『身近なサイエンスQ&A――自然のふしぎ』
『身近なサイエンスQ&A――自然のふしぎ』
田中忠芳 (著)、エド・ジェイコブ (訳)
雨上がりの空にかかる虹、稲妻が光ったあとに響く雷鳴、一週間が7日である理由――私たちの身のまわりには、科学でひも解けるふしぎがあふれています。本書では、気象、時間と重さ、電気・光・音という3つのテーマを通して、日常に潜む自然現象のしくみをQ&A形式でやさしく解説。ふとした疑問に立ち止まり、自然の奥深さや人類の探究心に思いを巡らせながら、科学を読む楽しさを味わえる一冊です。
山久瀬洋二からのお願い
いつも「山久瀬洋二ブログ」「心をつなぐ英会話メルマガ」をご購読いただき、誠にありがとうございます。
これまで多くの事件や事故などに潜む文化的背景や問題点から、今後の課題を解説してまいりました。内容につきまして、多くのご意見ご質問等を頂戴しておりますが、こうした活動が、より皆様のお役に立つためには、どんなことをしたら良いのかを常に模索しております。
21世紀に入って、間もなく25年を迎えようとしています。社会の価値観は、SNSなどの進展によって、よりミニマムに、より複雑化し、ややもすると自分自身さえ見失いがちになってしまいます。
そこで、これまでの25年、そしてこれから22世紀までの75年を読者の皆様と考えていきたいと思い、インタラクティブな発信等ができないかと考えております。
「山久瀬洋二ブログ」「心をつなぐ英会話メルマガ」にて解説してほしい時事問題の「テーマ」や「知りたいこと」などがございましたら、ぜひご要望いただきたく、それに応える形で執筆してまいりたいと存じます。
皆様からのご意見、ご要望をお待ちしております。どうぞよろしくお願い申し上げます。
※ご要望はアンケートフォームまたはメール(yamakuseyoji@gmail.com)にてお寄せください。
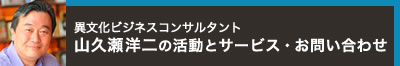


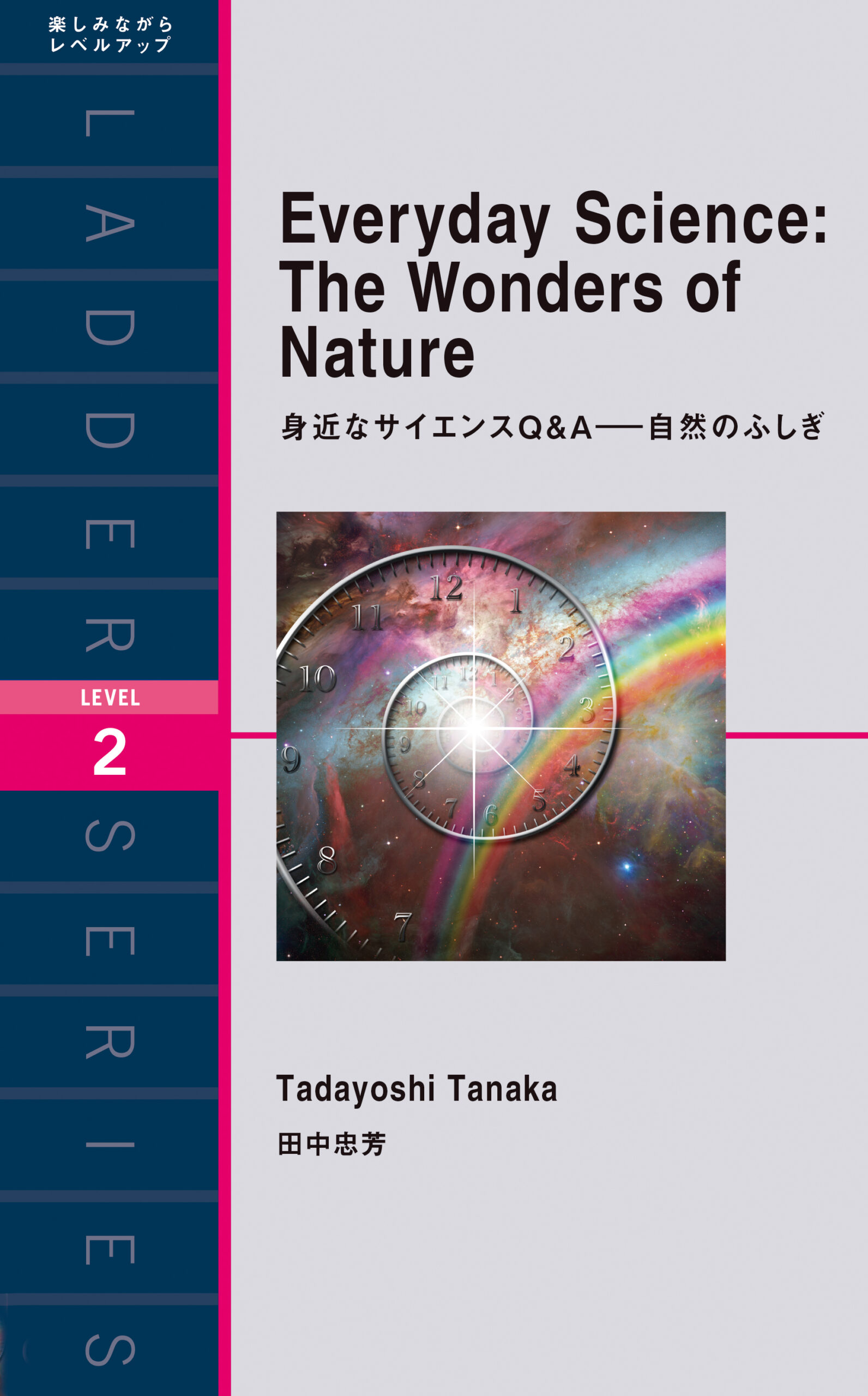 『身近なサイエンスQ&A――自然のふしぎ』
『身近なサイエンスQ&A――自然のふしぎ』