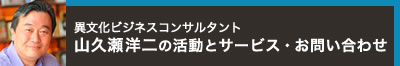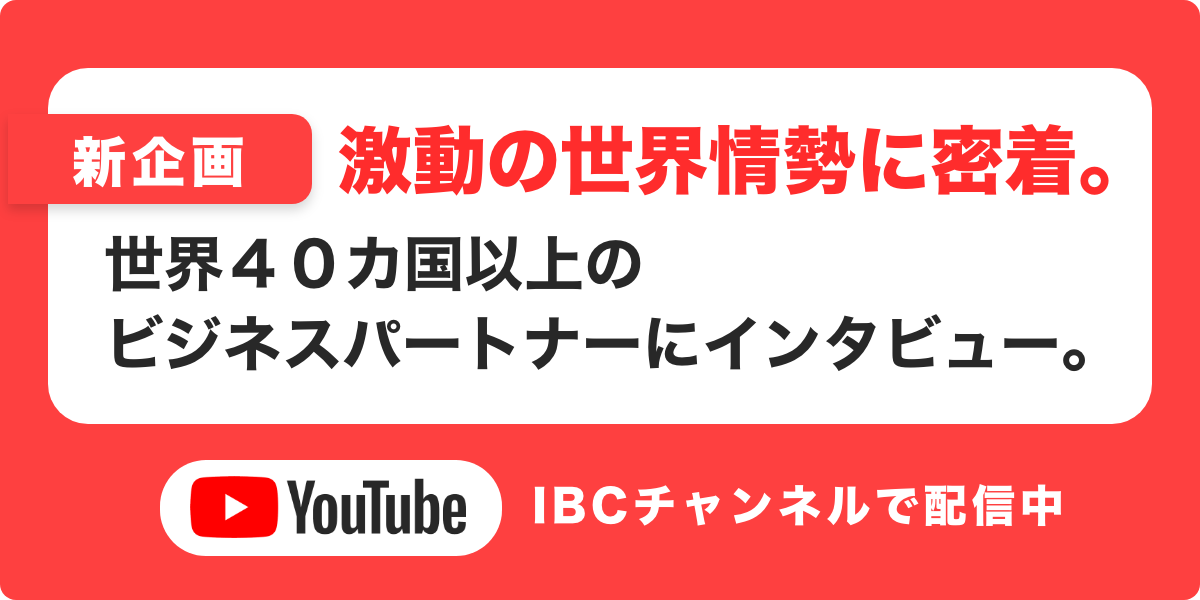Bears have killed a record 7 people in Japan this year.
2本の映像がうつし出すクマと人との共生のあり方
しかし、その一方で、我々が考えなければならない、もう一つのファクトについての報道が減っていることが気になります。つまり、よく言われる開発と温暖化などの気候変動によって追いつめられる動物の実態についてです。
これと同じことは知床半島などでもありました。クマは人の至近距離となるすぐそばで生活圏を持っていて、その境界線を越えようとすると漁師がイラン人と同じように叱りつけるのです。すると、クマはそのまますごすごと立ち去ってゆきます。
カナダの太平洋岸にはシロクマが生息する地域があります。ここでも現地の人々とクマの光景がみられます。そこでは餌は与えません。最初に紹介したイランの映像のように、人間は人間の、クマはクマの生活圏で静かに共存しているのです。
実は、これが以前ではごく当たり前の、人と自然とが共生する姿だったのです。クマは基本的には攻撃的な肉食の捕食者ではないので、人々はむしろその大きな姿に愛着すら覚えていたのです。
イランからの動画にせよ、この童話にせよ、その背景にあるのはクマと人との親密な関係です。

森を消失させた人はクマを駆除するしかないのか
森林を伐採して開発をしたのは人間です。気象異変にしても、さまざまな説はあるとしても、人間に全く責任がないかといえば疑問が残ります。そして、その結果クマが街に出没したとき、人々はそれを脅威としてクマをあたかも容赦なく人の命を奪う悪者のように報道をはじめたわけです。
ただ、その結果駆除されたクマへの心の痛みを忘れた一方的な報道には、多少うんざりしています。絶望的な環境のなかで食料を求めて人里をさまよい、その結果殺害されたクマに向けて、せめて心の中で手を合わせるような報道はないのかと考えさせられます。
それは、北海道でクマによる犠牲者がでたときのニュースを一緒にみていたときのことでした。
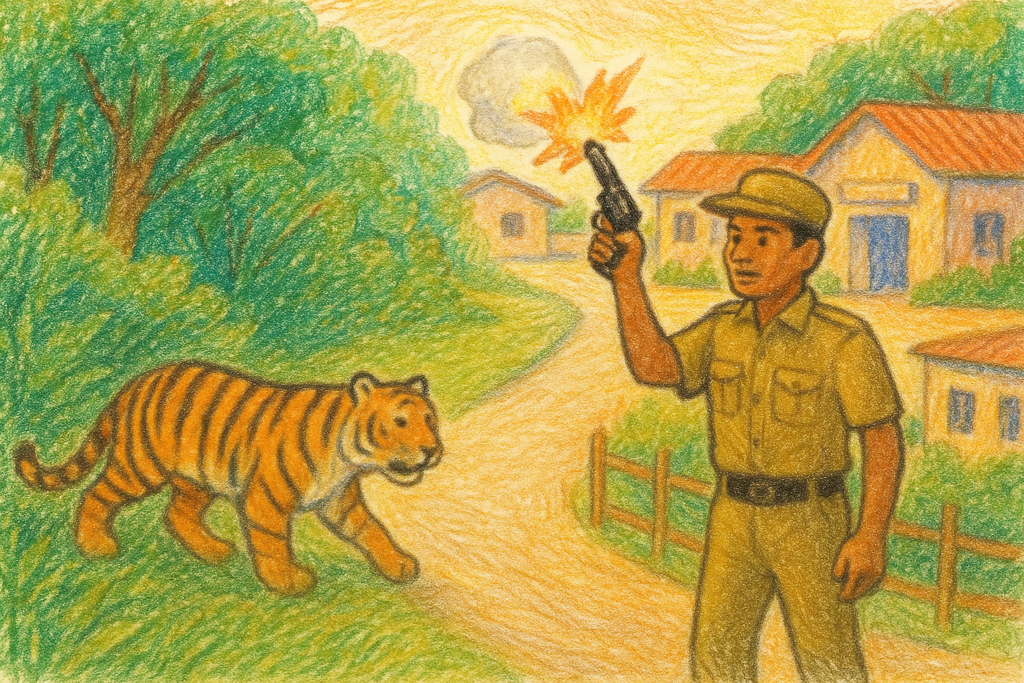
世界からも問われている人と野生動物との共生
* * *
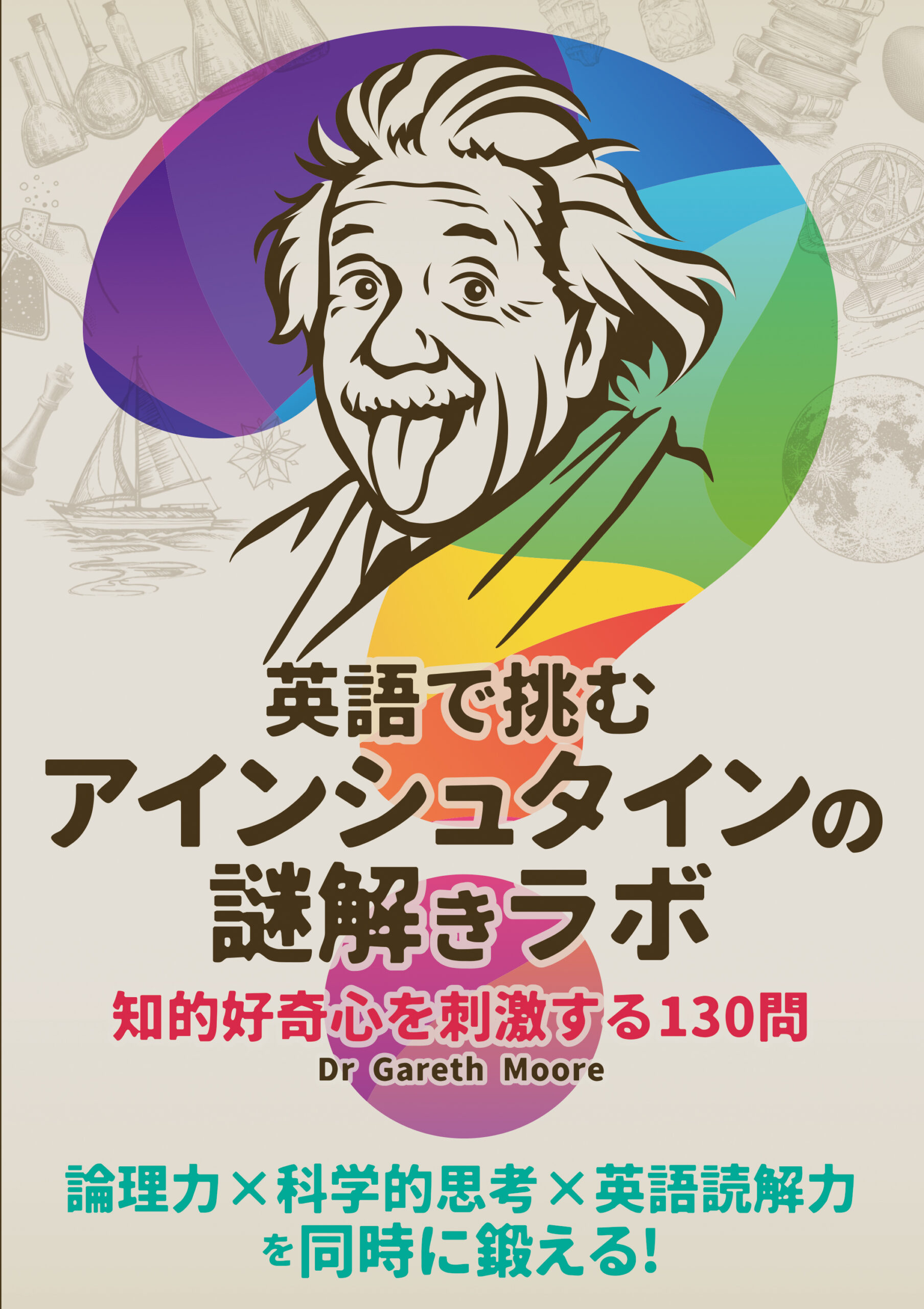 『英語で挑む アインシュタインの謎解きラボ』Dr Gareth Moore (著)
『英語で挑む アインシュタインの謎解きラボ』Dr Gareth Moore (著)
科学系の謎解きに挑みながら、英語読解力と思考力を鍛える! 「天才」アインシュタインの発想にインスパイアされた、科学・数学・論理をテーマにした知的好奇心を刺激する130の“謎解き”に英語で挑む! 柔軟なひらめき、論理的な思考力、そして少しの英語読解力を駆使する本書の謎解きに、難しい専門知識は不要です。設問はすべて、想像力豊かな推論と常識を組み合わせて解くように設計されているから誰でも楽しく挑むことができ、英語を読み解く力と、考える力が身につきます。今までにない【英語×科学×謎解き】の楽しい一冊です!
山久瀬洋二からのお願い
いつも「山久瀬洋二ブログ」「心をつなぐ英会話メルマガ」をご購読いただき、誠にありがとうございます。
これまで多くの事件や事故などに潜む文化的背景や問題点から、今後の課題を解説してまいりました。内容につきまして、多くのご意見ご質問等を頂戴しておりますが、こうした活動が、より皆様のお役に立つためには、どんなことをしたら良いのかを常に模索しております。
21世紀に入って、間もなく25年を迎えようとしています。社会の価値観は、SNSなどの進展によって、よりミニマムに、より複雑化し、ややもすると自分自身さえ見失いがちになってしまいます。
そこで、これまでの25年、そしてこれから22世紀までの75年を読者の皆様と考えていきたいと思い、インタラクティブな発信等ができないかと考えております。
「山久瀬洋二ブログ」「心をつなぐ英会話メルマガ」にて解説してほしい時事問題の「テーマ」や「知りたいこと」などがございましたら、ぜひご要望いただきたく、それに応える形で執筆してまいりたいと存じます。
皆様からのご意見、ご要望をお待ちしております。どうぞよろしくお願い申し上げます。
※ご要望はアンケートフォームまたはメール(yamakuseyoji@gmail.com)にてお寄せください。