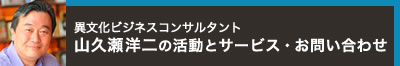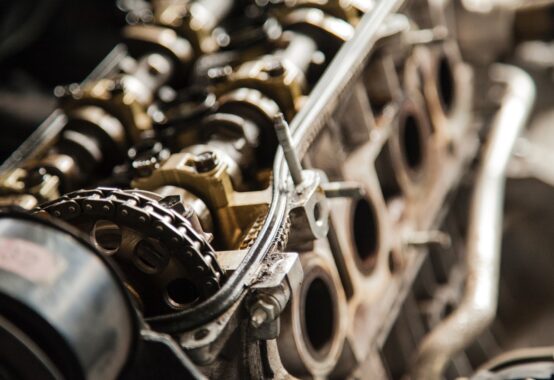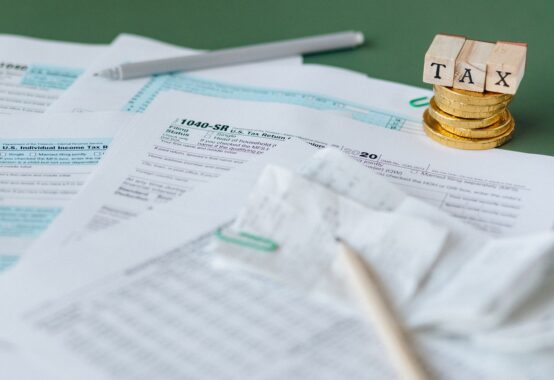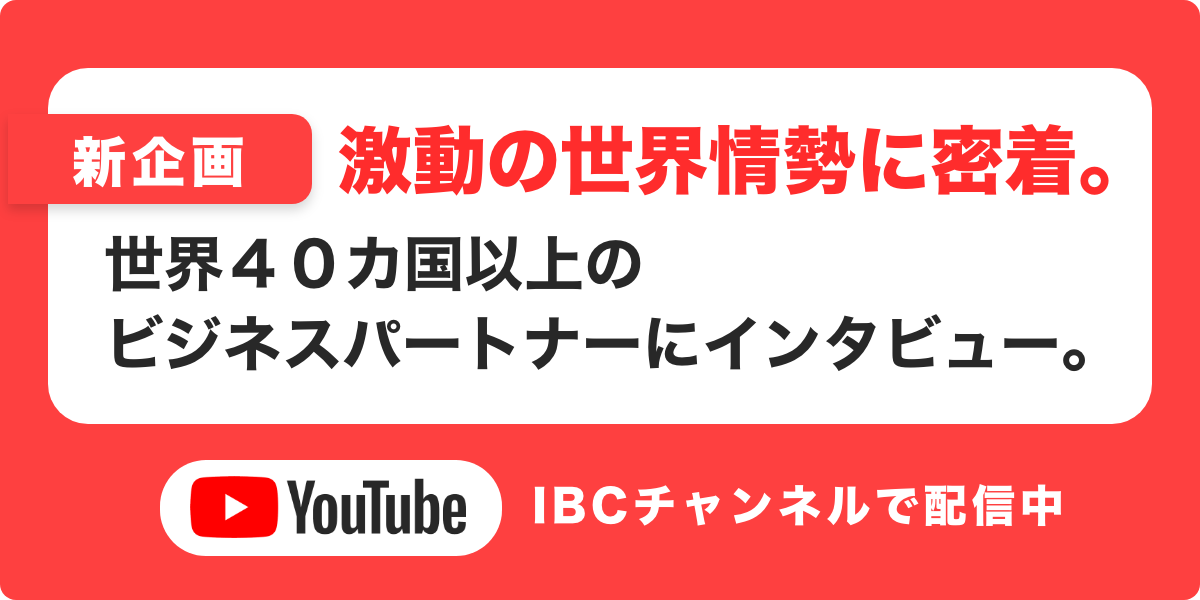Today, the Waymo Driver provides hundreds of thousands of weekly trips to satisfied riders across six major U.S. cities, driving over 1.6 million kilometers per week without a human behind the wheel.
(現在、ウェイモ・ドライバーは、米国の主要6都市に毎週数十万回の利用者に十分なサービスを提供し、人間のいないハンドルによって毎週160万km以上を走行している)
― Waymoの広報誌 より
自動運転タクシーの乗り心地と日本人のコメント
2018年暮れにグーグル傘下の
Waymo社がタクシーサービスをアリゾナ州フェニックスで始めてからすでに7年。今ではサンフランシスコやロサンゼルスという大都市でも、この運転手のいないタクシーを見かけるようになりました。
ロサンゼルスの郊外、太平洋に面したサンタモニカは、そんなWaymoを最も頻繁に見かける都市です。
実際に利用してみると、アプリによって配車を指示して、しばらくすると待っていた場所のほんの10メートルほど先に無人の車がやってきました。ドアを開けて乗り込みます。運転席に誰もいないのは不思議な光景です。ドアを閉めてシートベルトをつけ、運転席の脇のパネルにあるスタートの表示を押します。音楽が静かに流れ、そのまま車は発進しました。乗り心地は悪くありません。
———–
実際に無人タクシーに乗車した際の動画はこちら
⇒ https://youtube.com/shorts/4yUO_9Op8_U
———–
パネルには目的地である私の滞在するホテルまでの所要時間が18分と示されています。曲がり角になると、方向指示器の音が自動的に響き、あたかも透明人間でもいるかのようにハンドルがまわり、車は大通りに向けて右折しました。スピードはそれなりに出ていて、ときには周囲の車を追い越します。車線変更も適宜行い、大通りから路地へと曲がるときに、Waymoの前にいきなり車が飛び出して割り込んできたハプニングがありましたが、それも静かにかわして、そのまま夜道で視界の悪い路地を近道として選び、走行を続けます。再び大通りに出たときには、混み合った車線から別の車線にAIの判断で移動し、数台を追い抜いて、その後数分でホテルに無事到着しました。ぴったり18分間の走行でした。
日本のタクシー会社もWaymoの導入を検討しているというニュースは流れています。
そこで、iPhoneで動画にしたこの乗車体験を、いろいろな企業研修で日本企業に勤務する人に見せて、もしこのレベルでの導入を日本が行うとしたらどれくらい年月がかかるでしょうと問いかけると、ほとんどの人が日本での導入は難しいか、少なくとも10年はかかるのではというコメントが集まりました。
理由としては、日本では法改正や安全走行についての検査、さらに安全性への人々の同意にも相当の時間がかかるはずだというものでした。
中には、アメリカは道が広く歩行者もそれほど混み合っていないので、そもそも環境が異なっているという指摘もありました。サンタモニカの繁華街は日本とそれほど変わらない環境にあることを知っているだけに、日本は特殊な事情があるという主張は、まさに日本人ならではのコメントだなと思いました。

日本への導入を阻む「減点法」の価値観
そこで、もしものことを考えてみました。もしも日本でWaymoが事故を起こし、不幸にして犠牲者がでたらどうだろうと。確かに、マスコミや世論は大騒ぎをして、その計画自体が見送られる可能性もあるかもしれません。
アメリカで
自動運転の事故が発生したケースはいくつかあります。テスラの場合、事故率が通常の車よりも多いことが報道されています。ただ、その時のアメリカの対応は、被害者との訴訟は日本よりも大がかりですが、大方の見方は成功のために乗り越えなければならないリスクだというものでした。
1986年にスペースシャトル「
チャレンジャー号」が打ち上げ直後に空中分解する事故がありました。日系人の宇宙飛行士オニヅカ氏が殉職したことで、当時日本でも話題になりました。その折に当時のレーガン大統領が演説をし、スペースシャトルの運行を中止することはないとNASAに伝え、国民を鼓舞したことを覚えています。
日本の場合、何か事が起きると、その責任を追求し、誰かが辞任に追い込まれ、関係者はマスコミのバッシングに遭うことが頻繁にあります。確かに、この現象があるために、人々はリスクを回避し、慎重であることが良いことであるかのような優等生的発想に終始しがちです。また、こうしたバッシングの脅威があるために隠蔽も起こりがちです。
となると、Waymoの日本での運用にはまだまだ時間がかかるかもしれません。できない理由を挙げ、リスクを完璧に回避しているようなパフォーマンスを強調することをよしとしながら、減点法でビジネスを進める環境がいつの間にか日本には定着してしまったようです。
多くの研修の現場で、アジアから来て日本で働く人も、日本人とのコミュニケーションの難しさを指摘します。言語の問題以上に、物事の進め方があまりにもわかりにくいというのです。コンセンサスの取り方、合意の確認、さらには説得の方法など、規則が複雑で、コミュニケーションの方法も難解です。もちろん言語の問題もありますが、指示や指摘も曖昧で、アイディアを表明してもまず帰ってくるのは「それは困難だね」というネガティブな回答が多いといわれています。
この組織の問題が今、日本企業の生産性の障害になっています。特に海外との合弁事業など、グローバルな環境で日本企業が孤立してしまうことも多くあります。また、企業内でも海外から来た従業員の離職率が高くなり、企業に従順ではあるものの、力量に欠ける外国人のみが高い給与で組織内に残る傾向も指摘されています。

日本企業の緻密さに柔軟性と未来志向を
Waymoでホテルに到着したとき、小さなハプニングがありました。指定したホテルの入り口に入った直後に停車し、無事に目的地に到着したと私に伝えたのです。そこからホテルの玄関までは100メートルほどあり、そこを重たい荷物を持って歩いてゆきました。
しかし、この小さなミスは、きっとアメリカ企業にとってはどうでもよいことだという許容範囲のはずです。そのおおらかさが、技術の進歩にとっては必要なのでしょう。
世界的に競争が激化する中で、日本の企業に求められる柔軟性と未来志向の企業文化の育成は、緻密で知られる日本の企業活動の長所に付加されなければならない重要な課題かもしれません。
* * *
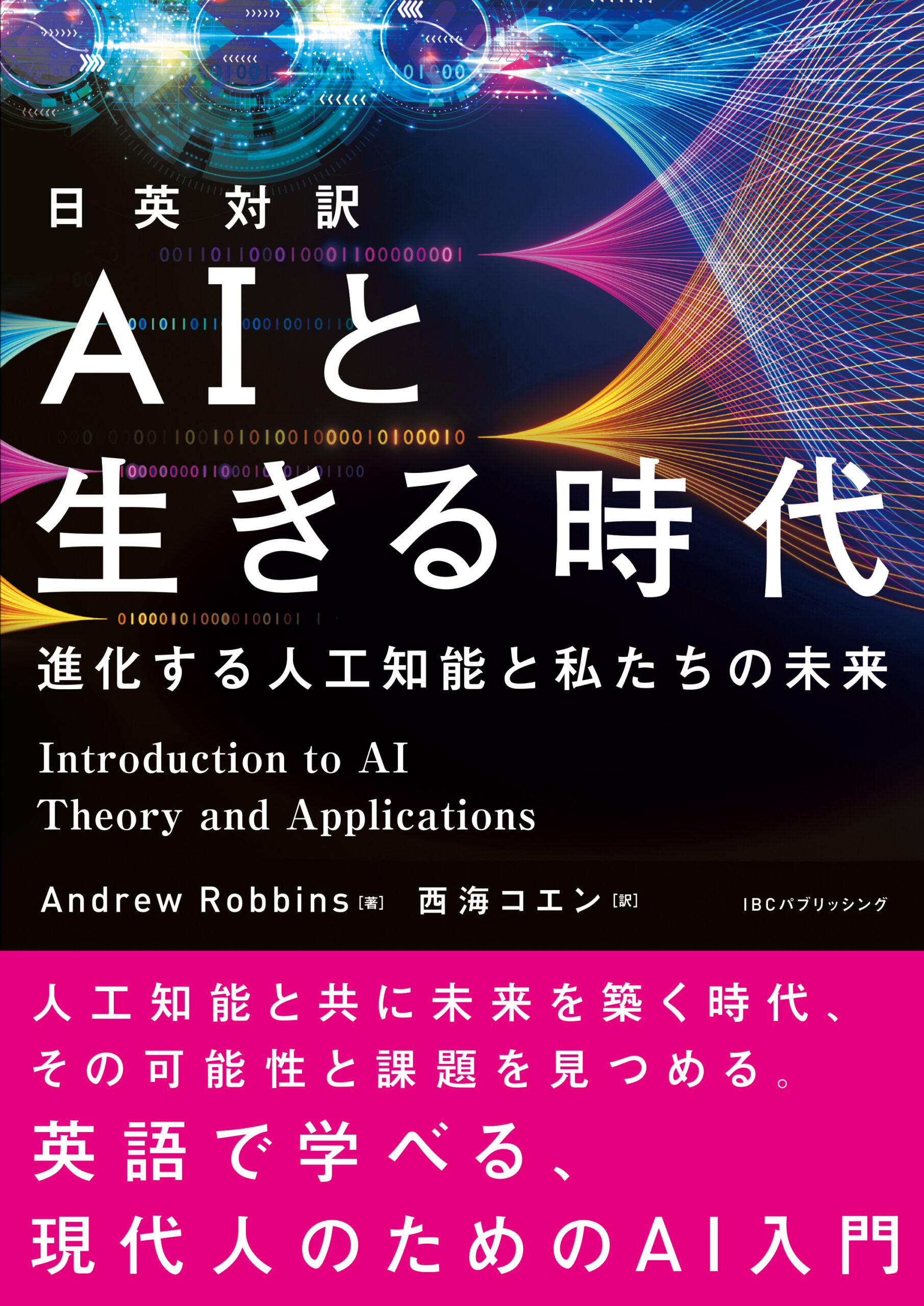 『日英対訳 AIと生きる時代』
『日英対訳 AIと生きる時代』
アンドリュー・ロビンス (著)、西海コエン (訳)
今日、人工知能(AI)はどこにでもあります。私たちの日常生活に大きな影響を及ぼすようになったその能力は驚異的なスピードで進歩しています。AIとはいったい何なのでしょうか? 使うべき道具なのか、恐れるべき武器なのか、はたまたおしゃべりをする友好的な仲間なのでしょうか? 本書では、私たちの身の回りで活用されている「AI」の歴史や概念、そして未来について日英対訳でわかりやすく解説します。理系英語に触れたい学習者にもオススメの一冊です!
山久瀬洋二からのお願い
いつも「山久瀬洋二ブログ」「心をつなぐ英会話メルマガ」をご購読いただき、誠にありがとうございます。
これまで多くの事件や事故などに潜む文化的背景や問題点から、今後の課題を解説してまいりました。内容につきまして、多くのご意見ご質問等を頂戴しておりますが、こうした活動が、より皆様のお役に立つためには、どんなことをしたら良いのかを常に模索しております。
21世紀に入って、間もなく25年を迎えようとしています。社会の価値観は、SNSなどの進展によって、よりミニマムに、より複雑化し、ややもすると自分自身さえ見失いがちになってしまいます。
そこで、これまでの25年、そしてこれから22世紀までの75年を読者の皆様と考えていきたいと思い、インタラクティブな発信等ができないかと考えております。
「山久瀬洋二ブログ」「心をつなぐ英会話メルマガ」にて解説してほしい時事問題の「テーマ」や「知りたいこと」などがございましたら、ぜひご要望いただきたく、それに応える形で執筆してまいりたいと存じます。
皆様からのご意見、ご要望をお待ちしております。どうぞよろしくお願い申し上げます。
※ご要望はアンケートフォームまたはメール(yamakuseyoji@gmail.com)にてお寄せください。
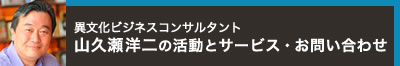


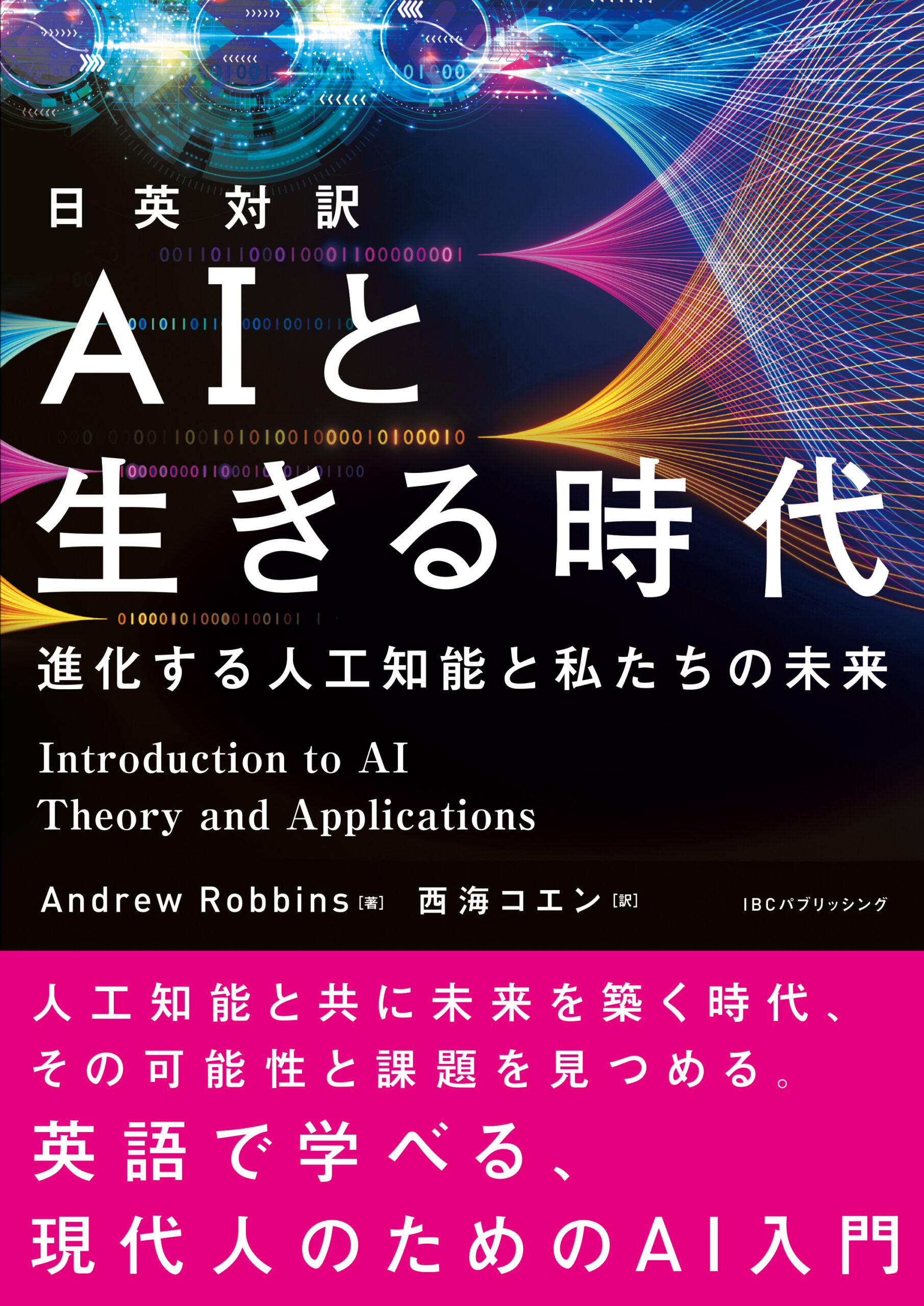 『日英対訳 AIと生きる時代』
『日英対訳 AIと生きる時代』