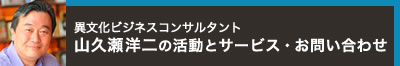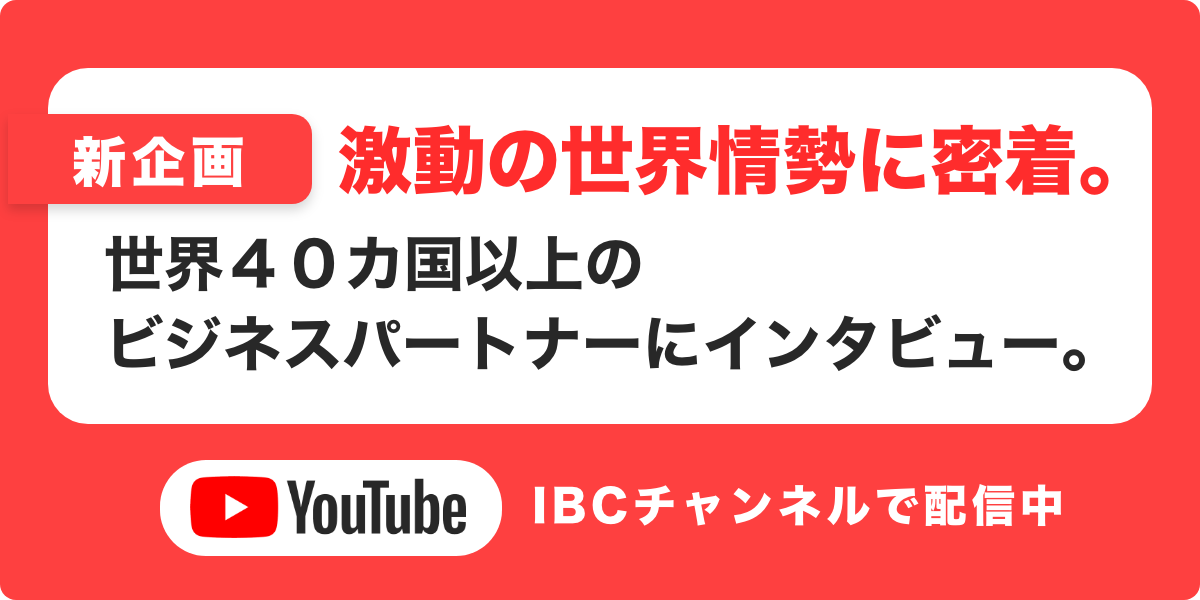One-third of elementary school students in Japan do not like learning English, according to a 2021 poll, an 8% rise since 2013. The pressure of taking proficiency tests is eroding children’s engagement with studying English and its benefits.
(2021年の調査では、日本の小学生の3人に1人が英語学習を嫌っていて、2013年から8%増加した。能力試験を受けるプレッシャーが、子どもたちの英語学習への意欲を損ない、英語を学ぶことのベネフィットから遠ざけている)
― Japan Times より
日本人の英語能力は「世界92位」?
日本人の英語のレベルがアジアでも最低に近い、というニュースをよく耳にします。実際、日本の英語教育が受験テクニックに偏っているために、実践力に難があることは昔から指摘されていることです。
しかし、今年になって、多くの報道機関が日本人の英語能力の国別世界ランクが92位だとして、同時にAIで検索しても、同様の回答がでている状況をみて、その信憑性に素朴な疑問を抱いたのです。
よく調べると、その情報源は留学および語学教育についての世界的なネットワークを持つEFコーポレートラーニング社であることがわかりました。さらに調べてみると、彼らの英語能力検定試験を自発的に受験した受験者数が400名以上の国をピックアップして、その採点を元に割り出したランキングであるということで、そうであれば、その評価にどこまで信憑性があるのかが気になってきます。
英語が国語ともいえるインドが69位で、同様のフィリピンが22位という結果も気になります。というのも、これらの国は今成長株ではありますが、貧富の差が激しく、一人当たりの所得は決して高くはありません。そうなれば、こうしたテストを受験する人は当然ある程度収入があり、教育も受けている人に限られているはずです。であれば、受験者の英語力はかなり高くなるはずです。こうした同じ社会環境の背景を持つ国で、これだけの格差が出てくるはずはないのです。
インド人には独特のアクセントがあり、概ね文法力の査定でのミスが起きがちだということはよく指摘されます。しかし、もしアクセントをテストで評価するとしたら、世界言語である英語とは何かという根本的な問いかけをしなければなりません。英語は国際間でのコミュニケーションを向上させるために必要な言語で、特定の国の発音だけを基準にして、その能力を査定していいのかと思うからです。
すなわち、こうした世界ランキングを公表する場合、一体どのような属性に依拠してテストを行なったのかというはっきりとした背景説明が欲しいのです。
さらに、同社の発表したランキングによれば、ロシアが44位で韓国が50位とのことですが、ロシアと韓国とでは国土の大きさも人口も差がありすぎます。その中でどの地域の人が受験したのかという状況によって、結果に大きな違いがでてくるはずです。ランキングの査定が都市と地方とを差別なく網羅した結果なのか、それともどちらもモスクワやソウルといった大都市の有名校だけを対象としたのかという背景の統一性も必要かもしれません。私の経験ではロシアの地方都市で、英語でコミュニケーションをすることは極めて困難だった記憶があるからです。
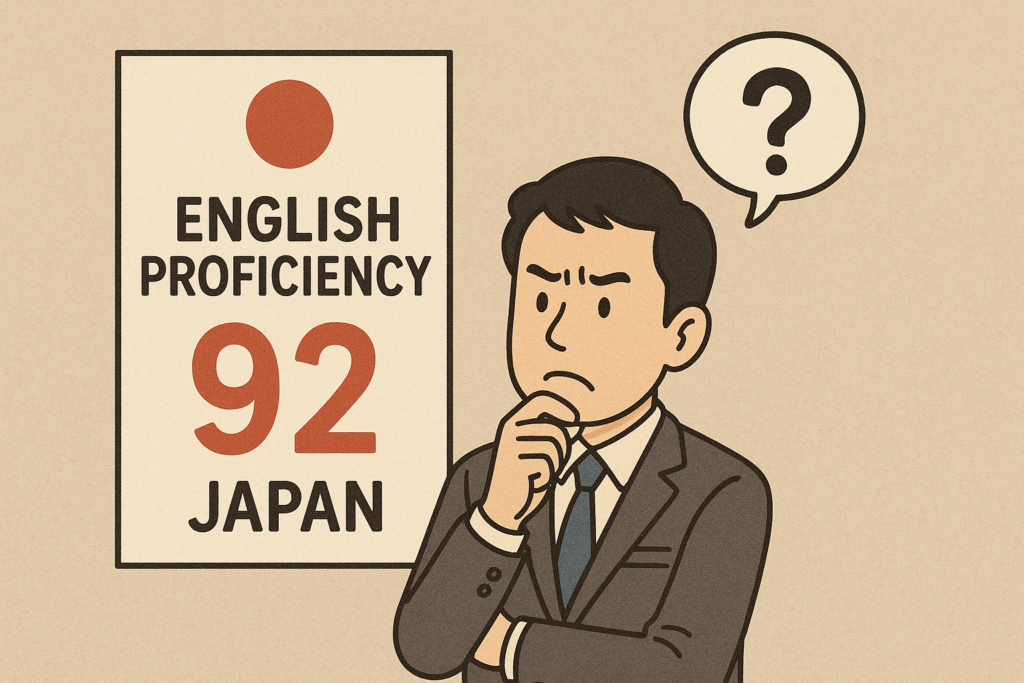
世界53か国を訪れた経験からみると
私は今まで53か国を訪ねています。その経験から実感するのは、英語が本当に簡便に通じる国は、北欧などヨーロッパの中の先進国に限られていて、韓国やたとえ英語を公用語とするフィリピンでも、ごく一般の庶民の英語力はかなり限られているということです。また、ブルガリアが16位と高位置につけていますが、確かに多くの人は英語を話します。しかし、私の実感では16位は高すぎます。
インドでは庶民の英語はあまりにも癖が強すぎて聞き取りにくいものです。しかし、同じ状況は英語が母国語のイギリスでも、隣国のアイルランドでも同様です。イギリスの事例をいえば、スコットランドの英語はインドでの庶民の英語と同様に聞き取ることは至難の技です。アイルランドの地方の英語は、時にはアメリカ人ネイティブが聞いても、その場でチェックをしない限り、ほぼ理解できません。
このことは逆に言えば、世界語であるがために、それぞれの地域の言語による発音の影響を英語が受けるのはごく当然であることを意味しています。
要は、片言の英語でも堂々と話し、完璧ではない文法や言い回しでも遠慮することなく話し、お互いにわからないところはチェックし合うコミュニケーション文化をもった地域の人は、概して英語力がある地域であると言っても差し支えないかもしれません。
その点では、日本人は完璧を求めすぎるために、会話を積極的にすることに戸惑いがあり、そのことによって英語力がないと誤解されるおそれは充分にあるはずです。しかし、もしそれが故に92位というレッテルを貼られるとしたら、その人が持っている本当の英語力をどこまで、どのような共通項をもって査定したのかという疑問が残ります。躊躇した行為だけが査定されて、その人が持っている単語力や読解力はどうなのかという疑問が残るのです。
確かに、日本は自らの英語能力に自信のない人が多い国でしょう。したがって、こうした結果が発表されると、ついつい「さもありなん」という感想が先行して、統計の信憑性への検証がないままに報道されてしまう傾向があることは事実です。また、そうした報道やネットでの拡散があれば、AIは自動的にこの結果をもって日本のランキングとしてしまいかねません。これが、AIによる記事が陥りやすい盲点であり、マスコミ報道の危険性ともいえるのです。
もちろん、日本の英語教育のあり方には多くの課題があることは事実です。TOEICなどのテストのスコアを上げることに集中しすぎて、実際のビジネスの現場などではほとんど役に立たない人が多くいることは否めない事実です。
しかし、わかっていただきたいのは、日本人の英語能力が世界最低のレベルかというとそうではないということです。読む、書く、聞く、話すという4技能を網羅して日本人の英語力をみれば、決して92位ではないはずです。

大切なのは“コミュニケーション”をする能力
大切なことは、こうしたあやふやな統計に一喜一憂して自虐的に英語力のなさを悲観するのではなく、より堂々と、カジュアルに、ミスをすることを恐れずに相手とコミュニケーションをする能力を養うことです。
そのことさえできれば、こうした統計資料を報道して評論する必要すらなくなるはずだと思うのです。そして何よりも、英語を含む学校での「勉強」を嫌いだと子ども達が思わないような教育者の工夫も、今求められている大きな課題のように思えるのです。社会人でいえば、日本人は潜在的に多くの英語情報を耳にし、書き、読んでいます。それをいかに有効的なコミュニケーション能力の向上に結びつけるかという教育のノウハウの開発も急務です。
そして、国別ランキングを語るのであれば、国民の総合力としての英語能力を査定する方法がない限り、こうした順位を安易にあたかも科学性があるかのように報道することは危険なことだと思うのです。
* * *
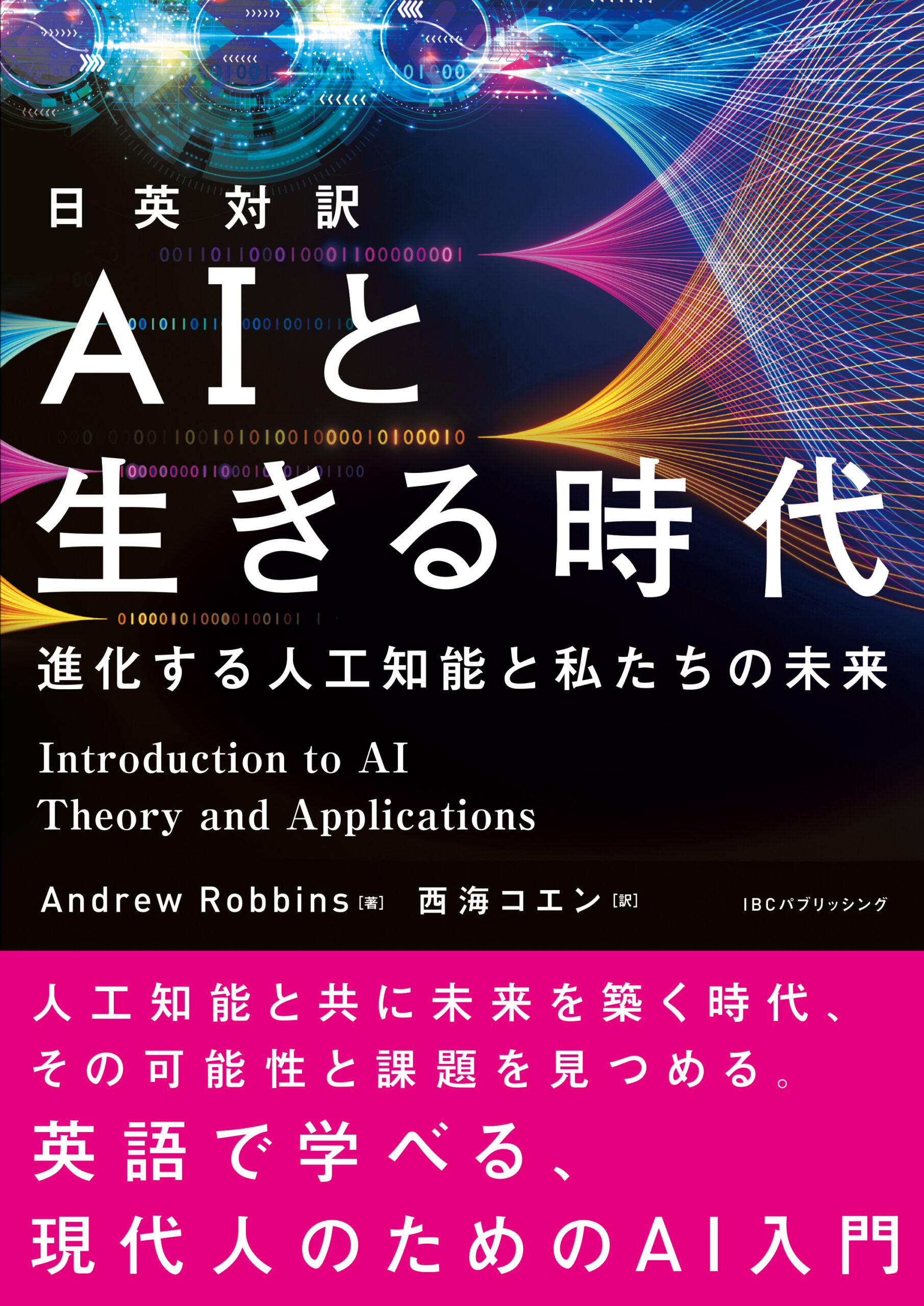 『日英対訳 AIと生きる時代』
『日英対訳 AIと生きる時代』
アンドリュー・ロビンス (著)、西海コエン (訳)
今日、人工知能(AI)はどこにでもあります。私たちの日常生活に大きな影響を及ぼすようになったその能力は驚異的なスピードで進歩しています。AIとはいったい何なのでしょうか? 使うべき道具なのか、恐れるべき武器なのか、はたまたおしゃべりをする友好的な仲間なのでしょうか? 本書では、私たちの身の回りで活用されている「AI」の歴史や概念、そして未来について日英対訳でわかりやすく解説します。理系英語に触れたい学習者にもオススメの一冊です!
山久瀬洋二からのお願い
いつも「山久瀬洋二ブログ」「心をつなぐ英会話メルマガ」をご購読いただき、誠にありがとうございます。
これまで多くの事件や事故などに潜む文化的背景や問題点から、今後の課題を解説してまいりました。内容につきまして、多くのご意見ご質問等を頂戴しておりますが、こうした活動が、より皆様のお役に立つためには、どんなことをしたら良いのかを常に模索しております。
21世紀に入って、間もなく25年を迎えようとしています。社会の価値観は、SNSなどの進展によって、よりミニマムに、より複雑化し、ややもすると自分自身さえ見失いがちになってしまいます。
そこで、これまでの25年、そしてこれから22世紀までの75年を読者の皆様と考えていきたいと思い、インタラクティブな発信等ができないかと考えております。
「山久瀬洋二ブログ」「心をつなぐ英会話メルマガ」にて解説してほしい時事問題の「テーマ」や「知りたいこと」などがございましたら、ぜひご要望いただきたく、それに応える形で執筆してまいりたいと存じます。
皆様からのご意見、ご要望をお待ちしております。どうぞよろしくお願い申し上げます。
※ご要望はアンケートフォームまたはメール(yamakuseyoji@gmail.com)にてお寄せください。
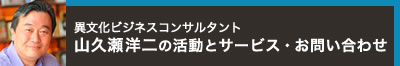
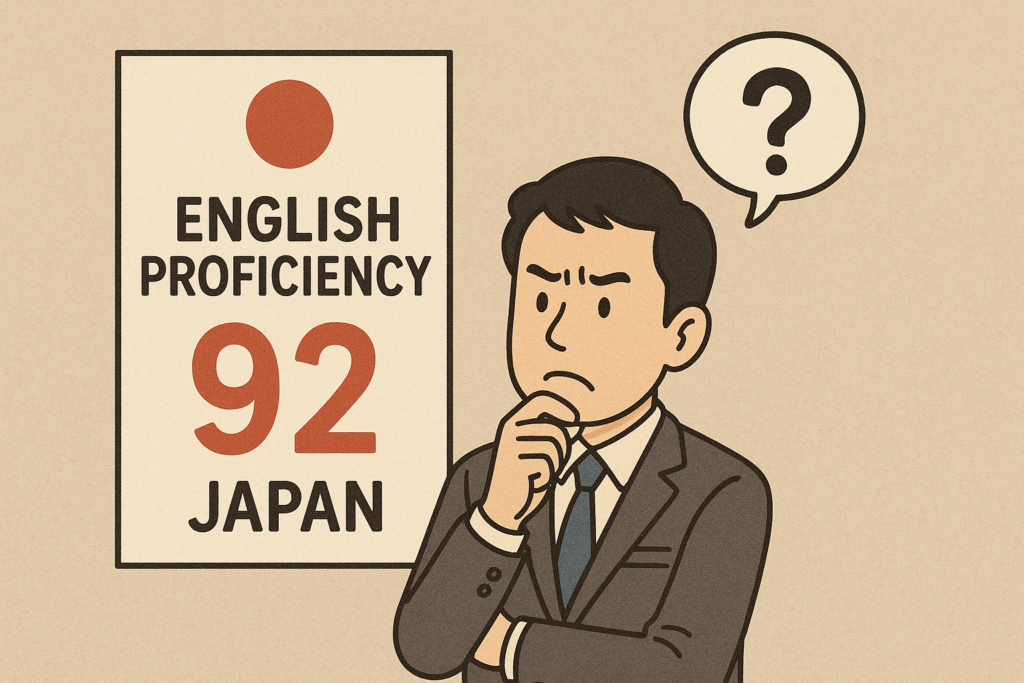

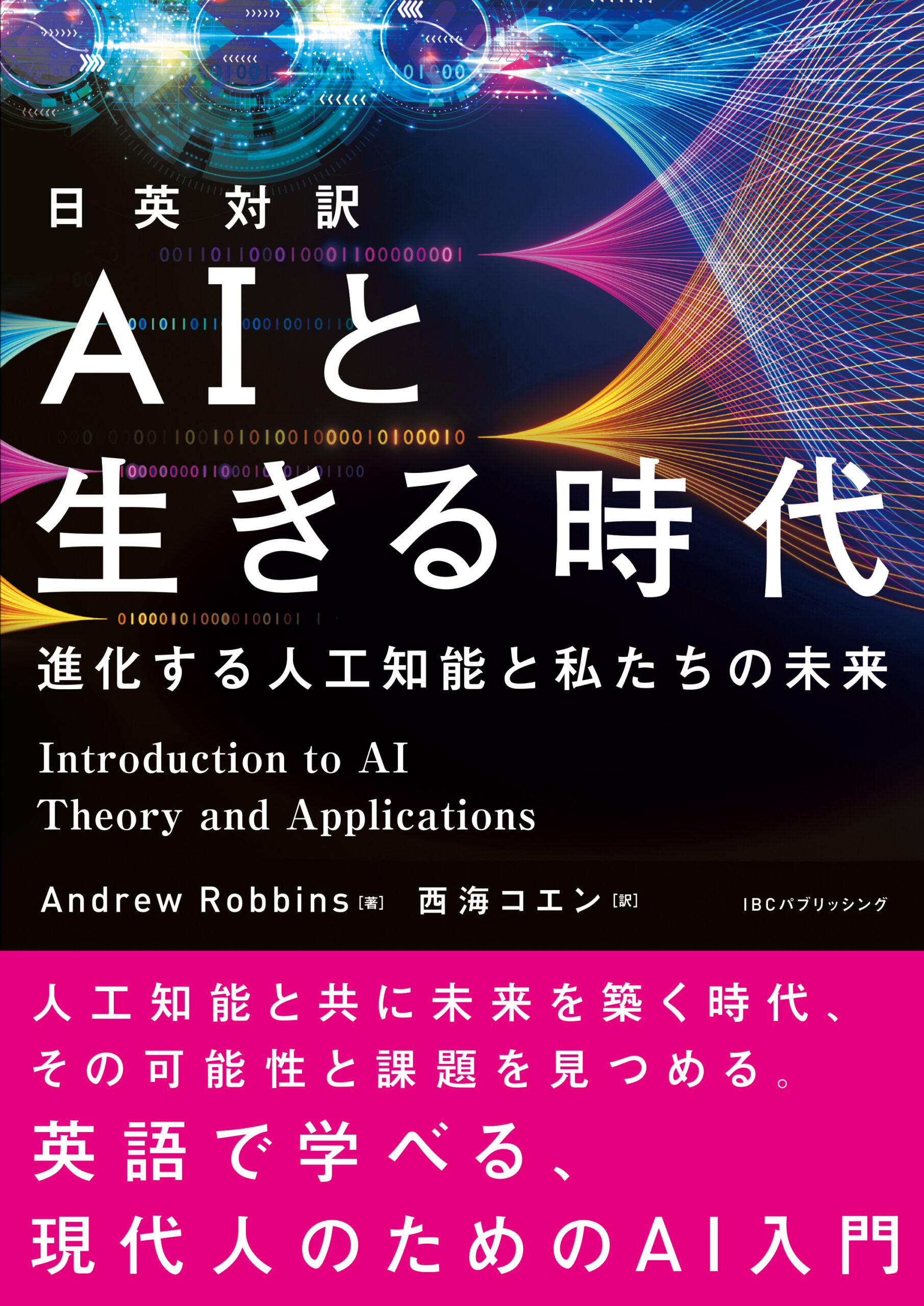 『日英対訳 AIと生きる時代』
『日英対訳 AIと生きる時代』