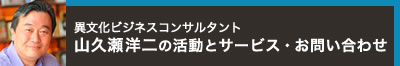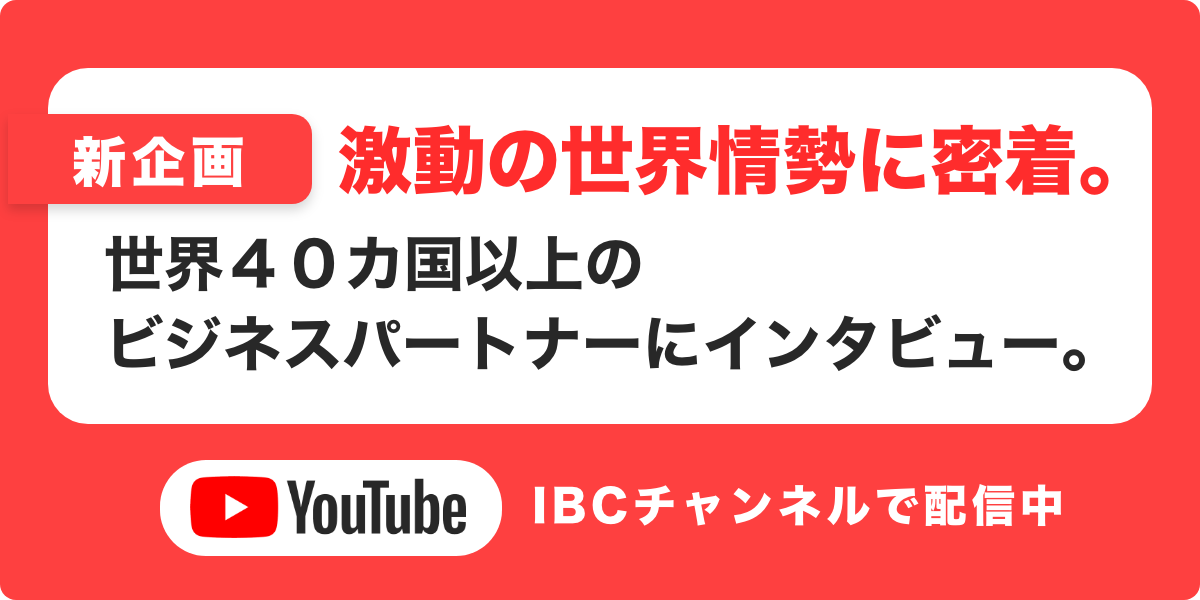He is Allah-One and Indivisible
(彼は唯一、分つことのできないアラーである)
― コーランの一節 より
アメリカで豊かに暮らすイスラム教徒の友人
今日は少し視点を変えて、宗教について語ってみたいと思います。
私の友人で、
ベルビューというシアトルの郊外に住むビジネスコンサルタントがいます。彼は中東世界とアメリカとをつなぐ仕事をしています。
彼自身はアフリカの小国
エリトリアに生まれ、戦火を逃れてサウジアラビアで育ちました。エリトリアは独裁者の国家で、無断で出国すること自体が命にかかわる厳罰に処せられるリスクを伴います。
友人は歩いて隣国まで逃れ、そこからサウジアラビアに移住したわけです。彼はそこで英語を学び、その後英語学校の経営者になります。その学校が成功し、そこで得た資金でアメリカに移住しました。彼の家のすぐそばにはマイクロソフトの本社があります。
彼は一見ごく普通のアメリカの黒人の風貌をもっています。彼は典型的な中産階級よりは少し上のクラスの生活をしています。広い芝生の前庭のある、アメリカの豊かさを象徴するような家に住んでいます。
しかし、一歩家の中に入ると、そこはイスラム社会です。昼食に招かれたとき、家の居間には彼の知人や親戚が絨毯の上に座ってくつろいでいました。女性の人影はなく、誰もが一目でイスラム教徒だとわかるような風貌をしています。玄関を開けた瞬間に、外国にワープしたかのような錯覚に陥るのです。中東風の昼食は豪華でした。彼の妻はパキスタン人ですが、実はまだ会ったことがありません。昼食中も、ダイニングテーブルに通されたときは、そこは男性だけの世界なのです。
彼には優秀な息子が2人います。その年長の息子はもうすぐ妻を迎えます。パキスタンの親戚の知り合いが紹介したお見合い結婚で、まだ新婦の顔を知りません。新婦が慣れないアメリカに馴染めるのか、人ごとながら不安がよぎります。
一度、インドの
ムンバイで、アラブ系の一家と公園で話したことがあります。彼らは新郎新婦と新郎の両親とで、ムンバイに立ち寄って数日を過ごし、そのまま新郎の住むアメリカに行くところだったのです。新婦が黒い衣装に包まれた顔から、まだあどけない目でこちらを見ていたことを思い出したのです。
ベルビューに住む友人とは、2年に一度ぐらいの頻度で会っています。彼は敬虔なイスラム教徒なのでお酒は飲みません。もちろん1日に5回のお祈りも欠かしませんし、ラマダンのときは日の出から日の入りまで断食をします。

イスラム教国家で政教分離が進まない背景とは
イスラム教世界の歴史をみると、イスラム世界で国家が興るとき、修道院でイスラム教の修行をしていた人物が、その教えの深淵に触れて新たな宗教運動をはじめ、それが宗教改革の波となって国家へと発展した経緯が多くあります。
中世にスペインの南部を支配していたイスラム王国の中に、北アフリカからスペインまでの広範な地域を支配していた王朝が2つあります。この2つの王朝はスペイン北部のキリスト教の王国の攻撃を退けて、スペインのイスラム文化の繁栄に貢献した国家ですが、このどちらもが、修道院での活動がその起源なのです。よくよく考えると、イスラム帝国を築いたイスラム教の始祖ムハンマドも、宗教者としての活動から国家を築いています。
最近では、イスラム教の原理主義者が世界から警戒されていますが、アフガニスタンを統治する
タリバンも、元はそうしたイスラム教の神学校で教育を受けた人々によって組織されたものでした。
このような背景が、イスラム教の国家で政教分離が進まない大きな理由のように思えます。
キリスト教の場合、中世のローマ・カトリックはイスラム教と同様に教義に縛られ、キリスト教の権威と世俗の政治との分離は進みませんでした。しかし、中世末期に宗教改革がはじまり、プロテスタントの人々がローマ・カトリックから離脱したことは、政教分離へと社会が転換する大きな背景となりました。プロテスタントは、個人と神との関係を重視し、その間にローマ教会のような権威は必要ないと主張したからです。個人個人の活動は教義に縛られないことから、世俗社会と教会の権威との分離が進んだわけです。その結果、市民という概念が定着し、後年の民主化運動にもつながっていったのです。
もちろん、ローマ・カトリックもその影響を否定することはできず、今回の
コンクラーベで教皇となったレオ14世も、時代に適したカトリック教会内部の改革にどう取り組むかが注目されているのです。
個々人の信仰を重んじる宗教と、教義を重んじる宗教との違いが、現代社会の中で民主主義の基本ともいえる政教分離を実践しやすい国家とそうでない国家との相違を形成したわけです。
私の友人は敬虔なイスラム教徒ですが、彼は今プロテスタントが多数派のアメリカ社会で暮らしています。したがって、彼の心の中には、まさに現在のカトリックを信じる14億の人々が経験しているような2つの思いが同居しているはずです。それは多様性を重んじ、民主的であるが故に自分を受け入れてくれたアメリカと、その中でそれでも伝統的な教義に忠実であろうとする自分との間に、しっかりと折り合いをつけてゆく思いであるといっても差し支えないはずです。

常に文化の違いを尊重し学び続けようとすること
近年、西欧社会でイスラム原理主義者によって起こされるテロの問題が注目されました。というのも、テロを起こす人々の多くが、イギリスやアメリカなどに住むイスラム系移民の2世であったからです。彼らが自らの多様性への偏見を感じたとき、その心の拠り所として、私の友人が生活の規範としているイスラム教の教義への極端な回帰現象がおきるのでしょう。
世界は、さまざまな文化が融合しながら進化してきました。イスラム教の教義にも、我々が心にとめなければならない素晴らしい哲学があります。その哲学が他の思想や宗教と対立するのではなく、尊重することによって刺激しあうとき、社会は発展してゆくはずです。私の友人も心の中では、まさにそうした葛藤と進化の波の中で、常に揺れながら折り合いをつけているはずです。
「アメリカに来て思ったことがあるよ。
それは彼らがどれだけ我々の社会や歴史に対して無知かということだ」
以前、夕食の席で彼がそうこぼしたことがありました。
それに頷いた私も、常に文化の違いを尊重するために学ばなければと自らに言い聞かせているのです。
* * *
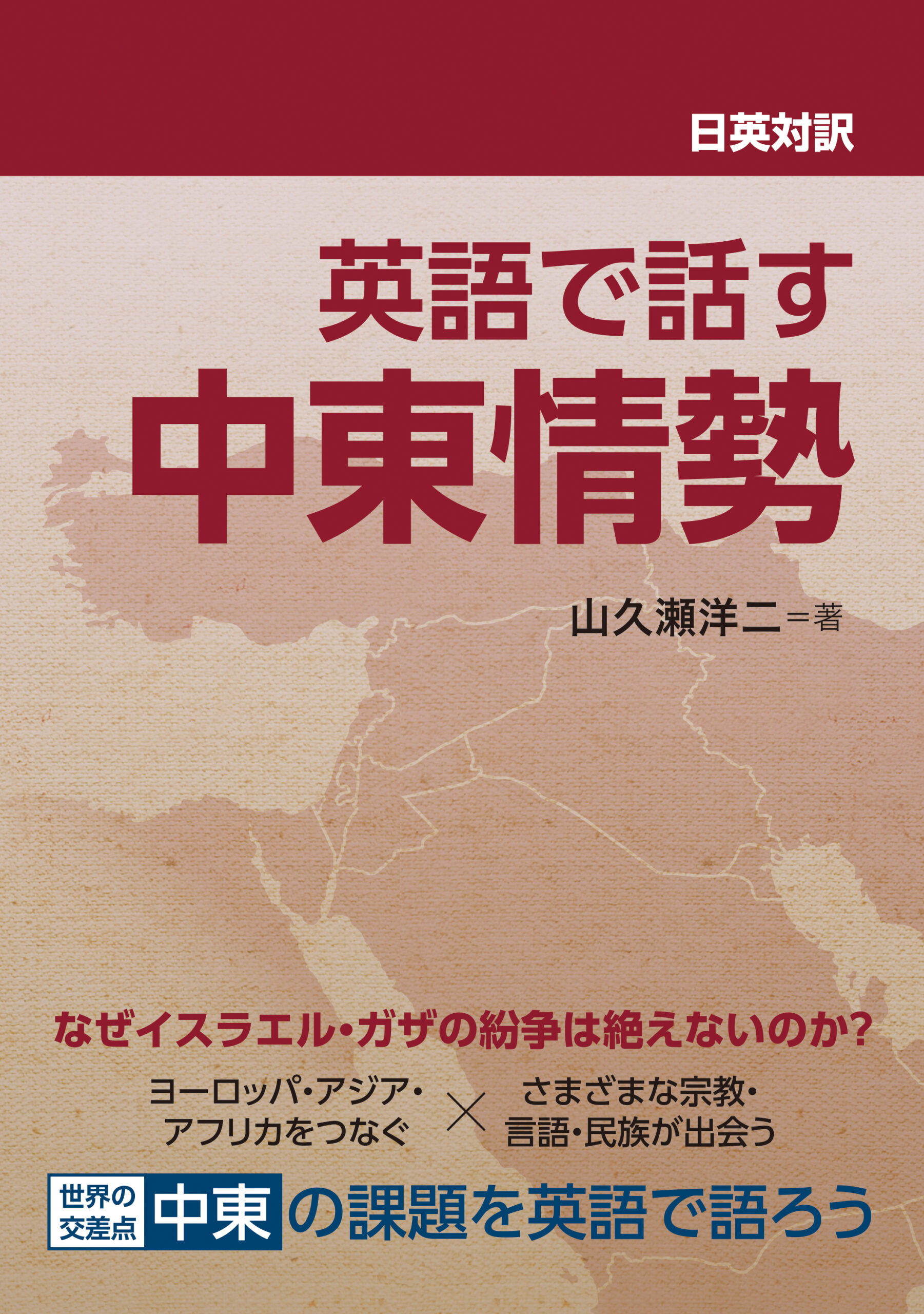 『日英対訳 英語で話す中東情勢』山久瀬 洋二 (著)
『日英対訳 英語で話す中東情勢』山久瀬 洋二 (著)
さまざまな宗教・言語・民族が出会う世界の交差点・中東の課題を、日英対訳で学ぶ! 2023年10月に始まったハマスによるイスラエルへの奇襲攻撃と、イスラエル軍によるガザ地区への激しい空爆と地上侵攻は世界に大きな衝撃を与えました。中東情勢の緊迫化は、国際社会の平和と安定、そして世界経済にも大きな影響を及ぼします。地理的にも遠く、ともすれば日本人には馴染みの薄い中東は、政治・宗教・歴史などが複雑に絡み合う地域です。本書では、3000年にわたる中東・パレスチナの歴史を概説し、過去、現在、そして未来へと続く課題を日英対訳で考察します。読み解くうえで重要なキーワードや関連語句の解説も充実!
山久瀬洋二からのお願い
いつも「山久瀬洋二ブログ」「心をつなぐ英会話メルマガ」をご購読いただき、誠にありがとうございます。
これまで多くの事件や事故などに潜む文化的背景や問題点から、今後の課題を解説してまいりました。内容につきまして、多くのご意見ご質問等を頂戴しておりますが、こうした活動が、より皆様のお役に立つためには、どんなことをしたら良いのかを常に模索しております。
21世紀に入って、間もなく25年を迎えようとしています。社会の価値観は、SNSなどの進展によって、よりミニマムに、より複雑化し、ややもすると自分自身さえ見失いがちになってしまいます。
そこで、これまでの25年、そしてこれから22世紀までの75年を読者の皆様と考えていきたいと思い、インタラクティブな発信等ができないかと考えております。
「山久瀬洋二ブログ」「心をつなぐ英会話メルマガ」にて解説してほしい時事問題の「テーマ」や「知りたいこと」などがございましたら、ぜひご要望いただきたく、それに応える形で執筆してまいりたいと存じます。
皆様からのご意見、ご要望をお待ちしております。どうぞよろしくお願い申し上げます。
※ご要望はアンケートフォームまたはメール(yamakuseyoji@gmail.com)にてお寄せください。
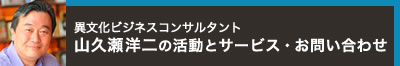
- Yamakuse Yoji’s World View 時事解説
- アラー, イスラム教, エリトリア, キリスト教, コンクラーベ, シアトル, タリバン, プロテスタント, ベルビュー, ムンバイ, ラマダン, レオ14世, ローマ・カトリック, 原理主義, 宗教改革, 政教分離


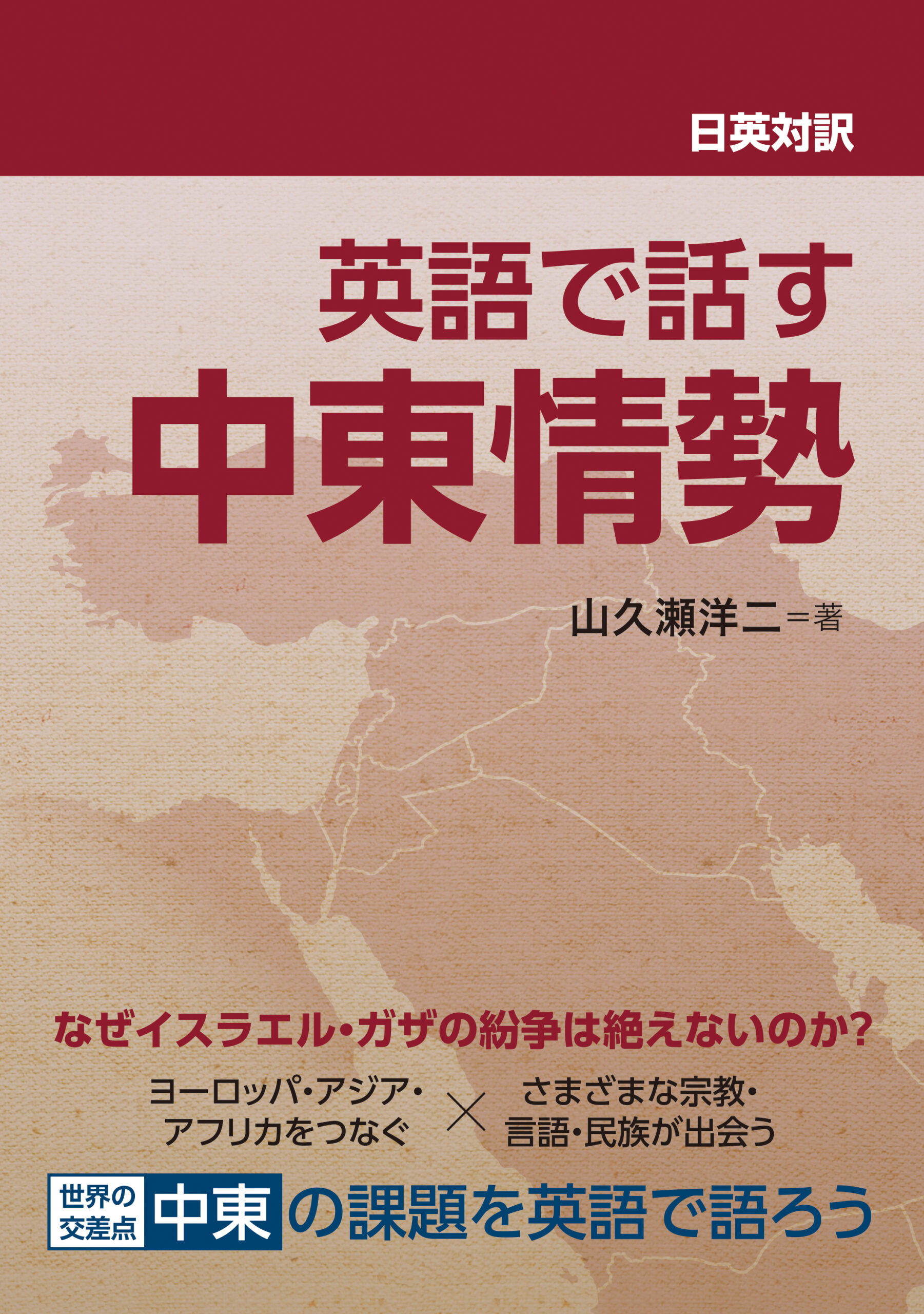 『日英対訳 英語で話す中東情勢』山久瀬 洋二 (著)
『日英対訳 英語で話す中東情勢』山久瀬 洋二 (著)