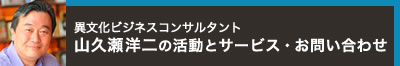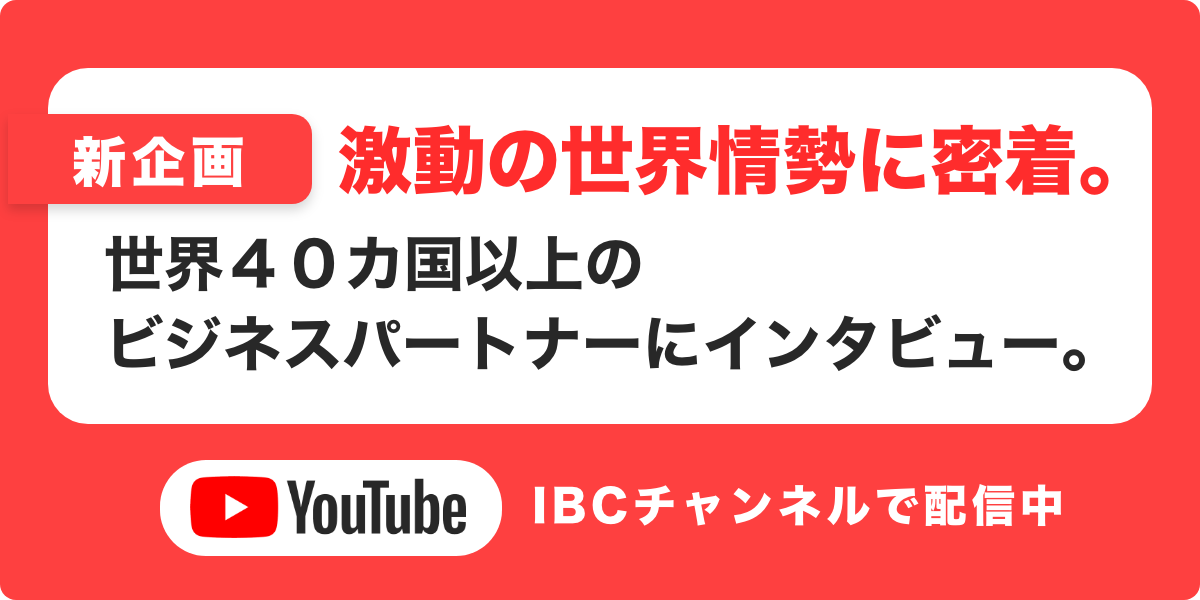When you learn to accept Kuuki o yomu as one form of communication, among others more familiar to you if you not originally from Japan, you can learn to use it to build bridges across cultures and relationships.
「空気を読む」日本社会のコミュニケーション
その言葉は、その場の雰囲気や人間関係、そこに置かれた人と人との状況を敏感に察知して、自らの対応を決めることを意味します。
「空気を読めないやつ」といえば、鈍感でその場の状況とは関係なく、自分だけの意思で動く人のことを指しています。もちろん、この表現は日本ではそのような人を批判するときに使用する言葉です。
一方で、あえて空気を読まずに、勇気ある発言をすることが必要な場合もあるはずです。会社などであまりにも理不尽な叱責を受けたり、指示を受けたりした場合、それに甘んじるのではなく、しっかりと自分の立場を主張することも、時には求められるからです。正義感が強ければ、むしろあえて空気を読まない方がいいこともあるはずです。

Compromiseが弱まる米国社会の治療薬として
これは哲学的には、さまざまな矛盾を解析してゆくなかで、高次元の法則を発見する弁証法を世間感覚で実践する言葉といっても差し支えありません。
日本の場合、日本人が空気を読みすぎて、その行為が社会の停滞を生んでいると思う人が増えているようにも思えます。逆に、アメリカでは自己主張が強すぎるために、そこに空気を注入する必要性を痛感しているのかもしれません。

「文化の違い」を「読む」価値観へと進化させること
しかし、当日になって式典に参加したとき、その理由が明快にわかったのです。台湾側は出席者に対して高価な贈り物を用意していました。日本側は、日本の常識に沿って、とりあえず相手の市長室に飾るための贈呈品とお菓子だけを用意して式典に臨んだのです。贈り物文化を大切な価値観とする台湾からみれば、参加者の数を事前にしっかりと把握することが、その予算と贈呈品の用意のためにどうしても必要だったのです。
スコットが語ることを日本流に理解すると、そこに日本の課題がみえてきます。日本の課題は、「空気を読む」習慣をよりグローバルに進化させる教育の普及にあるのではないでしょうか。日本人の伝統的な価値観が閉鎖的な価値観へと収れんしたとき、そこには偏狭なナショナリズムか、醜い自己陶酔の姿しか残らないはずです。
* * *
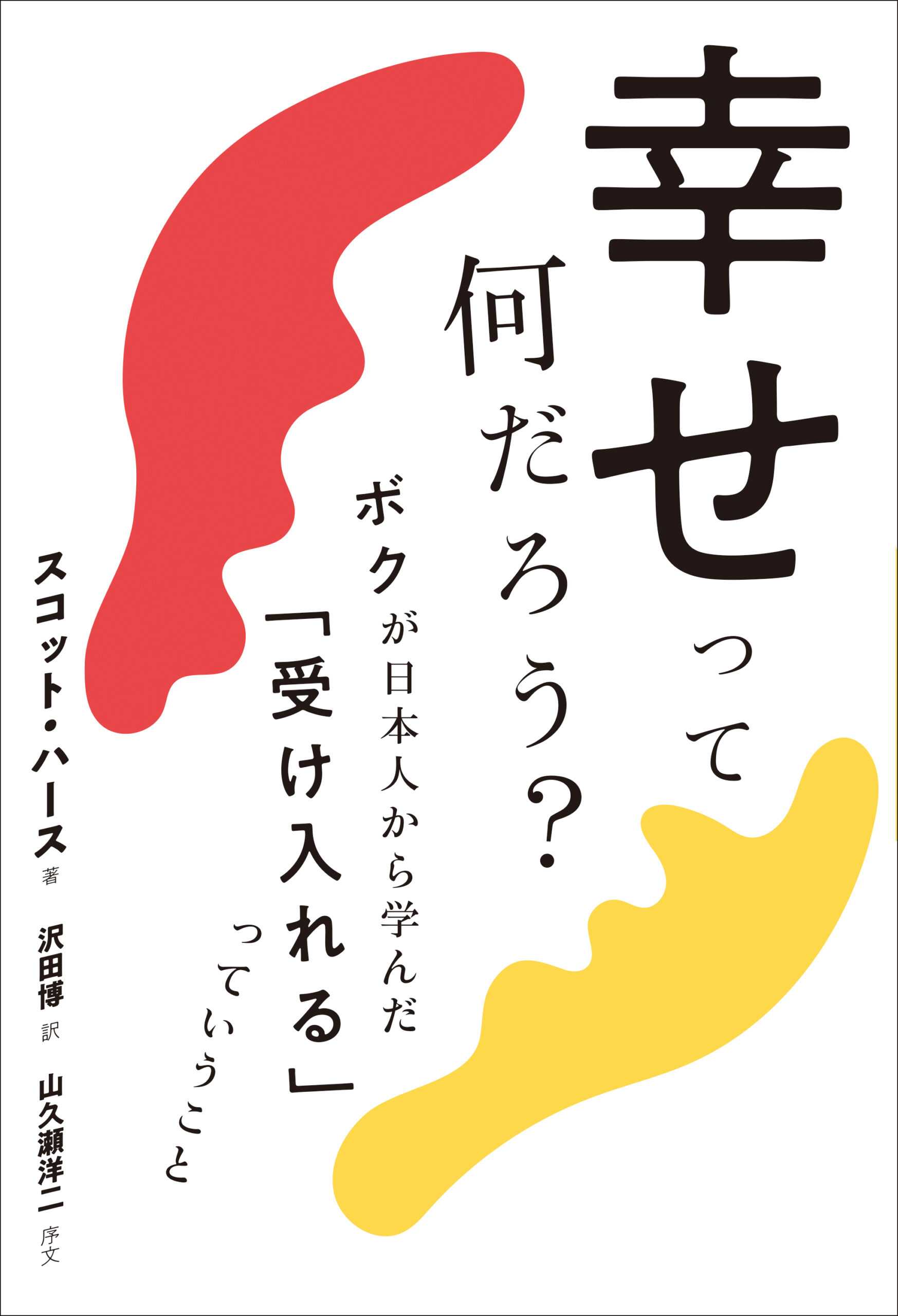 『幸せって何だろう? ボクが日本人から学んだ「受け入れる」っていうこと』スコット・ハース (著)、沢田博 (訳)
『幸せって何だろう? ボクが日本人から学んだ「受け入れる」っていうこと』スコット・ハース (著)、沢田博 (訳)
アメリカ人臨床心理学者が感じた個人主義の「幸福感」の限界。そして、日本的な調和の概念から見出した「幸せ」になる思考法。アメリカで出版され、世界11カ国で発売。ニューヨーク・タイムズ他、多数の有名紙で紹介され、話題を集めた書籍の翻訳版。人間にとっての「幸せ」について、著者が属する西洋社会(個人主義)の問題点と、日本の集団的な調和の精神から見出した「学び」を綴る。集団への帰属に必要な「受け入れる」という日本人の価値観を起点に、さまざまな行動様式の背景にある日本人の「思い」や「知恵」について考察し、西洋社会にも取り入れるべき点を、実体験をもとに解説。日本人の価値観や抱く意識を丁寧に紐解きながら解説する本書は、日本人にも自らの文化を見つめ直す機会と新たな気づきを与えてくれる。
山久瀬洋二からのお願い
いつも「山久瀬洋二ブログ」「心をつなぐ英会話メルマガ」をご購読いただき、誠にありがとうございます。
これまで多くの事件や事故などに潜む文化的背景や問題点から、今後の課題を解説してまいりました。内容につきまして、多くのご意見ご質問等を頂戴しておりますが、こうした活動が、より皆様のお役に立つためには、どんなことをしたら良いのかを常に模索しております。
21世紀に入って、間もなく25年を迎えようとしています。社会の価値観は、SNSなどの進展によって、よりミニマムに、より複雑化し、ややもすると自分自身さえ見失いがちになってしまいます。
そこで、これまでの25年、そしてこれから22世紀までの75年を読者の皆様と考えていきたいと思い、インタラクティブな発信等ができないかと考えております。
「山久瀬洋二ブログ」「心をつなぐ英会話メルマガ」にて解説してほしい時事問題の「テーマ」や「知りたいこと」などがございましたら、ぜひご要望いただきたく、それに応える形で執筆してまいりたいと存じます。
皆様からのご意見、ご要望をお待ちしております。どうぞよろしくお願い申し上げます。
※ご要望はアンケートフォームまたはメール(yamakuseyoji@gmail.com)にてお寄せください。